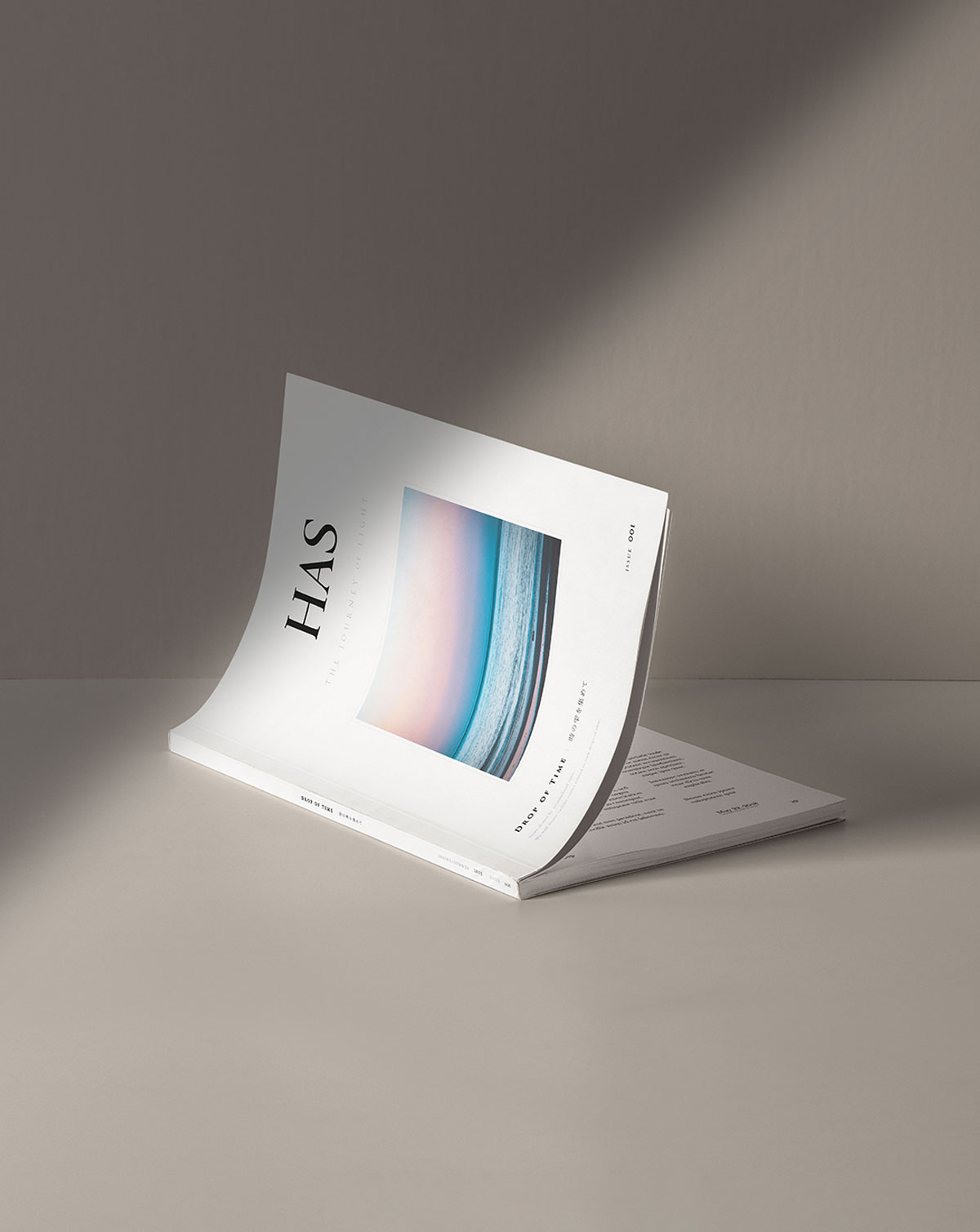さざなみの記憶と滋賀の祈り
Shiga

Shiga
この土地は、そんな豊かな自然に導かれるように、古の時代から数々の物語が紡がれて来た。
そんなこの地に息づく物語に耳を澄ましてゆくと、ある途方もない祈りの言葉に辿り着いた。
その祈りの言葉は、遥かなる創造力の源泉となり、不朽の名作「銀河鉄道の夜」を生んだ、日本を代表する作家・宮沢賢治にも大きな影響を与えたとも言われている。
滋賀の地に息づく様々な物語を辿りながら、途方もない祈りの言葉を紐解いてゆく「さざなみの記憶と滋賀の祈り」。
中編の題名は「光の記憶」。
今回の物語では、ある一冊の本が紡いだ途方もない祈りの言葉を紐解きながら、その祈りに宿る光の記憶を辿ってゆく。
- text / photo HAS
of Light
of Light

映し出された真理
最澄が願文を残してから12年もの月日が経とうとしていた。
その間、自ら掲げた信念を決して曲げることなく、比叡山に身を投じ、ただひたすらに仏教の学びを深めていった。
比叡山には、「論湿寒貧(ろんしつかんぴん)」という言葉がある。
夏は、琵琶湖からの水蒸気のため湿気がひどく、冬の寒さもまた厳しい。
そんな比叡山の自然環境の厳しさを表現したものだ。
しかし、その厳しい環境が最澄自身の内省を深め、その内に眠る霊性を磨いていった。
心の奥底に映る湖面は澄み渡り、鏡のような美しさを湛えていたのだろう。
そして、その澄み切った心で最澄がすくい上げたのは、ある一冊の本に綴られていた、ひとつの言葉だった。

その一冊の本とは、「法華経」と呼ばれる経典。
それは「諸経の王」とも称され、日本だけでなくアジア各地で読み継がれて来た経典だった。
この経典の中で紡がれる物語は、インドのある山を舞台に展開される。
- text / photo HAS
Reference :
-
「図説・滋賀県の歴史」
- 編集:
- 木村 至宏
- 出版:
- 河出書房新社
-
「琵琶湖 - その呼称の由来」
- 著者:
- 木村 至宏
- 出版:
- サンライズ出版
-
「京滋びわ湖山河物語」
- 著者:
- 沢 潔
- 出版:
- 文理閣
-
「近江古代史への招待」
- 著者:
- 松浦 俊和
- 出版:
- 京都新聞出版センター
-
「人類哲学序説」
- 著者:
- 梅原 猛
- 出版:
- 岩波新書
-
「最澄 - 京都・宗祖の旅」
- 著者:
- 百瀬 明治
- 出版:
- 淡交社
-
「鎌倉仏教」
- 著者:
- 平岡 聡
- 出版:
- 角川選書
-
「滋賀県の百年」
- 著者:
- 傳田 功
- 出版:
- 山川出版社
-
「老子」
- 翻訳:
- 小川 環樹
- 出版:
- 中央公論新社
-
「銀河鉄道の夜」
- 著者:
- 宮沢賢治
- 出版:
- 青空文庫
-
「セロ弾きのゴーシュ」
- 著者:
- 宮沢賢治
- 出版:
- 青空文庫
-
text / photo :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら、それぞれの光に出会う、ライフストーリーマガジン。 世界中の美しい物語を届けてゆくことで、一人一人の旅路を灯してゆくことを目指し、始まりました。About : www.has-mag.jp/about