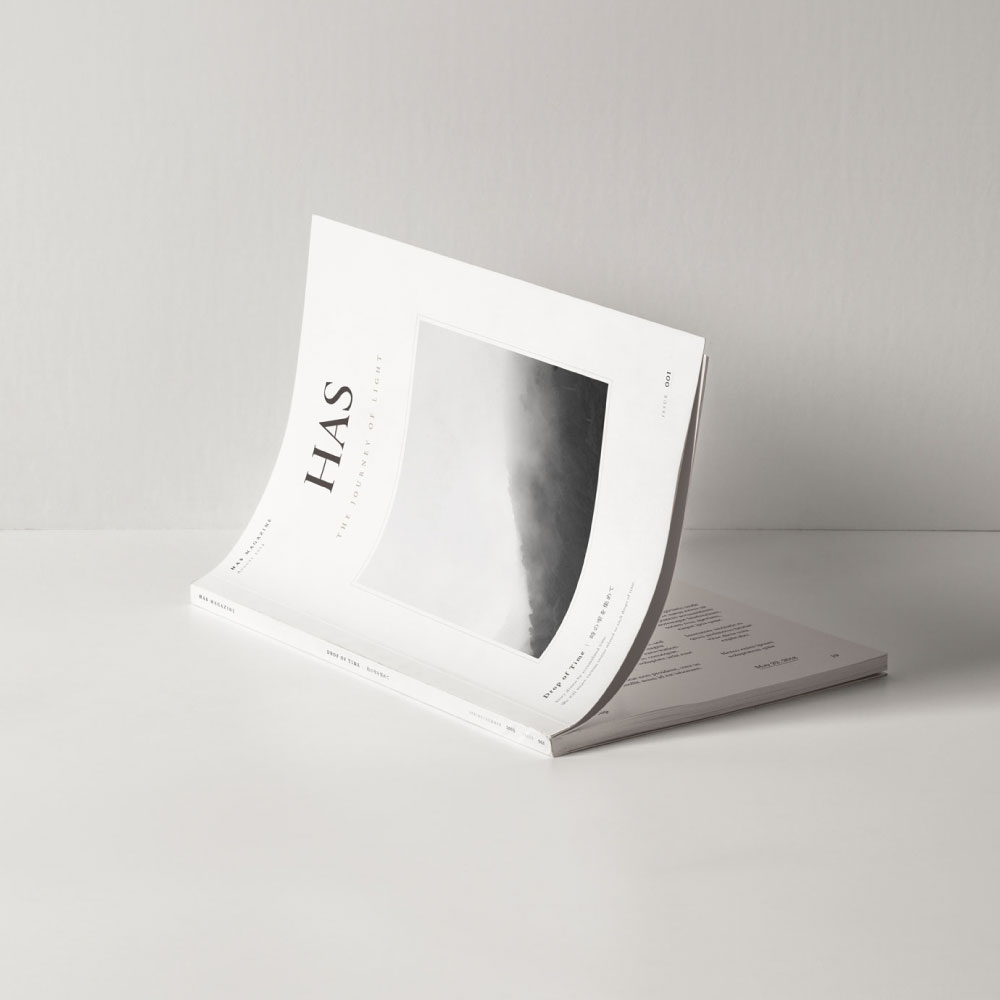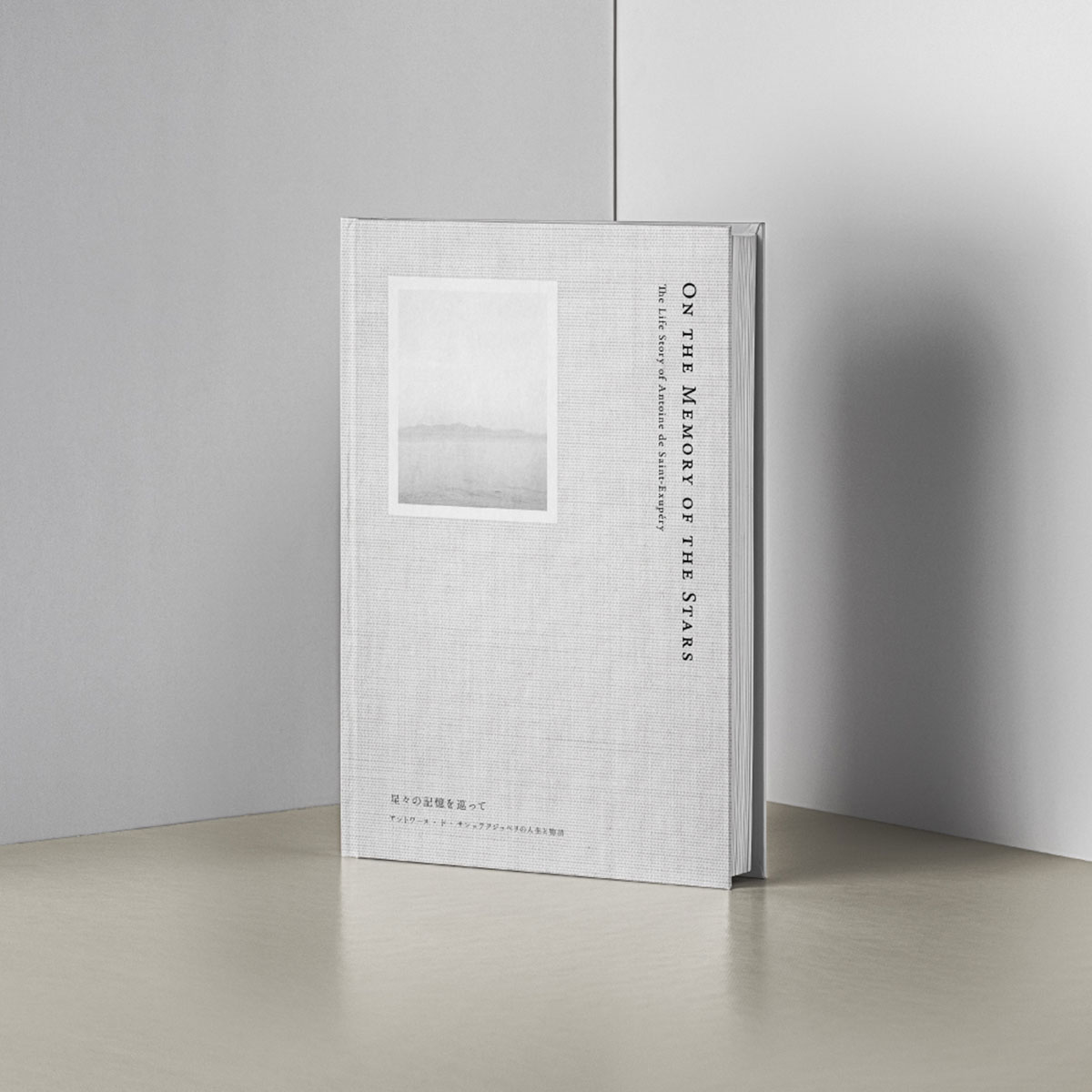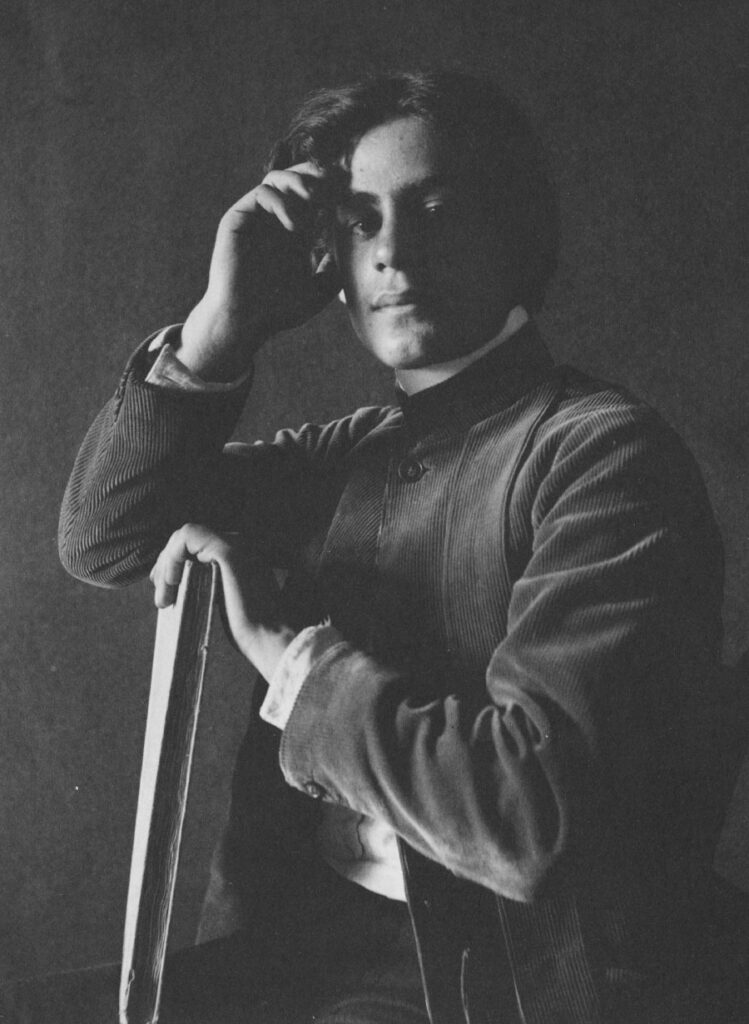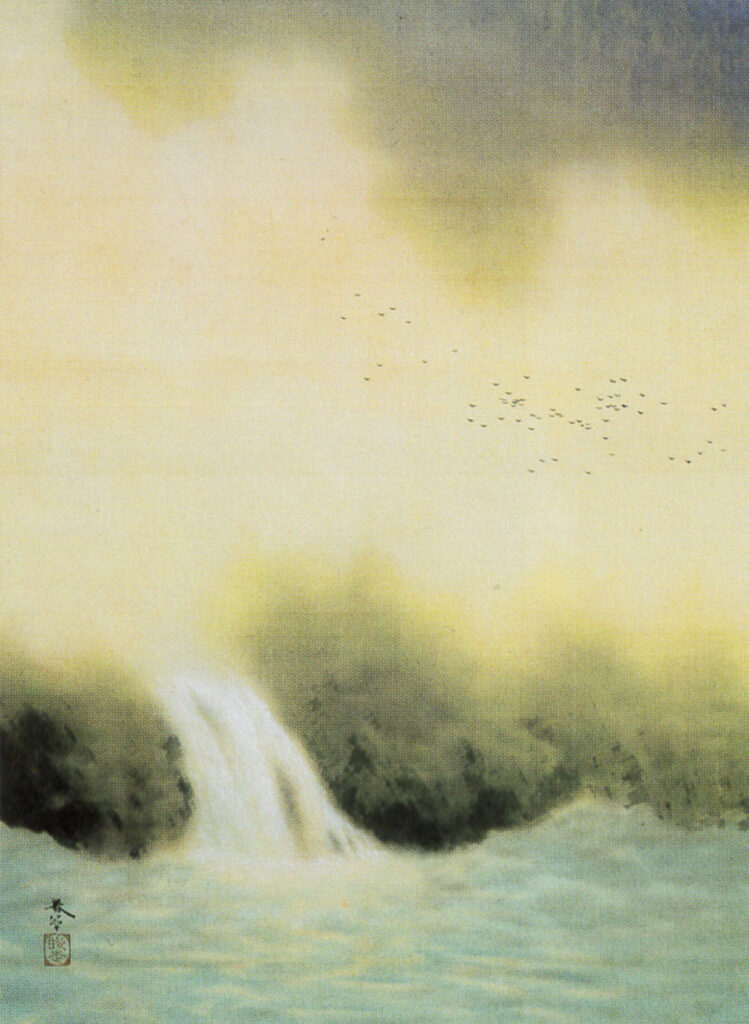[ 全4話 ]
光を描いた日本画家
菱田春草の物語
菱田春草の物語
Hishida
Shunso
Shunso
Hishida
Shunso
Shunso
全4話

Hishida
Shunso
Shunso
遡ること約120年前。
幾多の動乱を経て、江戸から明治への時代の大きな移り変わりの中で、日本は近代化を目指し、西欧の文化を積極的に吸収しながら、あらゆるものが大きく変革し始めていた。
そんな変わりゆく時代に共鳴するように、伝統的な日本画の世界でも、新たな変革の旗手となる一人の青年が現れた。
その青年の名は、菱田春草。
後に近代日本画の革命児とも称される彼は、それまでの伝統を打ち破り、新たな日本画の表現を打ち立てた。
しかし、その新しさゆえに数多くの批判を受け、36年の短い生涯の多くを不遇の中で過ごした。
春草が描いた、美しい色彩と繊細な光に彩られた様々な作品。
そんな作品の背景には、不遇の中で自らの意思を貫き、ひたむきに自身の表現を深め続けた、一人の画家の物語が流れていた。
彼が描いた様々な作品を辿りながら、その人生の物語を辿ってゆきたい。
幾多の動乱を経て、江戸から明治への時代の大きな移り変わりの中で、日本は近代化を目指し、西欧の文化を積極的に吸収しながら、あらゆるものが大きく変革し始めていた。
そんな変わりゆく時代に共鳴するように、伝統的な日本画の世界でも、新たな変革の旗手となる一人の青年が現れた。
その青年の名は、菱田春草。
後に近代日本画の革命児とも称される彼は、それまでの伝統を打ち破り、新たな日本画の表現を打ち立てた。
しかし、その新しさゆえに数多くの批判を受け、36年の短い生涯の多くを不遇の中で過ごした。
春草が描いた、美しい色彩と繊細な光に彩られた様々な作品。
そんな作品の背景には、不遇の中で自らの意思を貫き、ひたむきに自身の表現を深め続けた、一人の画家の物語が流れていた。
彼が描いた様々な作品を辿りながら、その人生の物語を辿ってゆきたい。
- text HAS
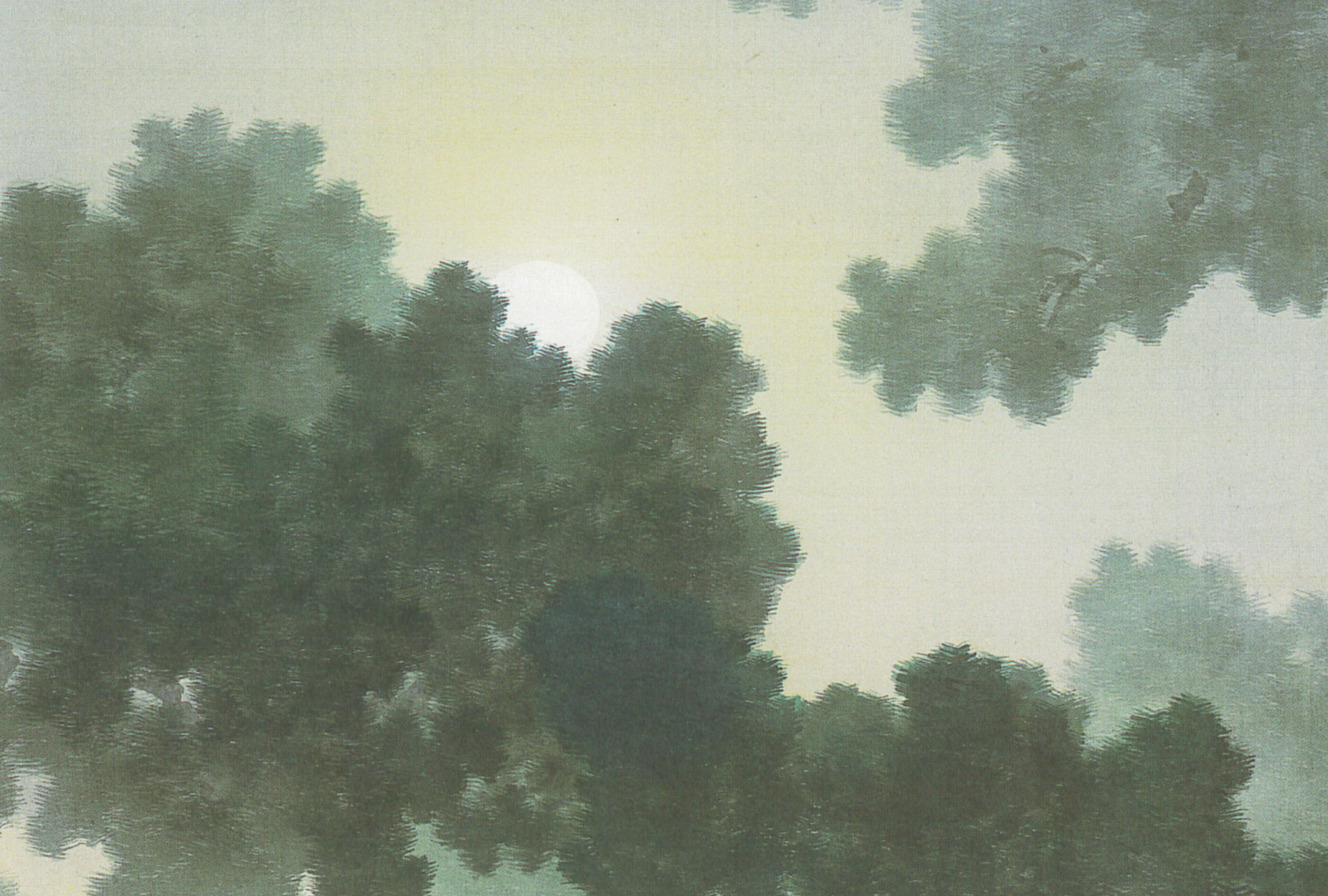
Chapter list
-
 [ 序章 ]光を描いた日本画家 菱田春草の物語
[ 序章 ]光を描いた日本画家 菱田春草の物語 -
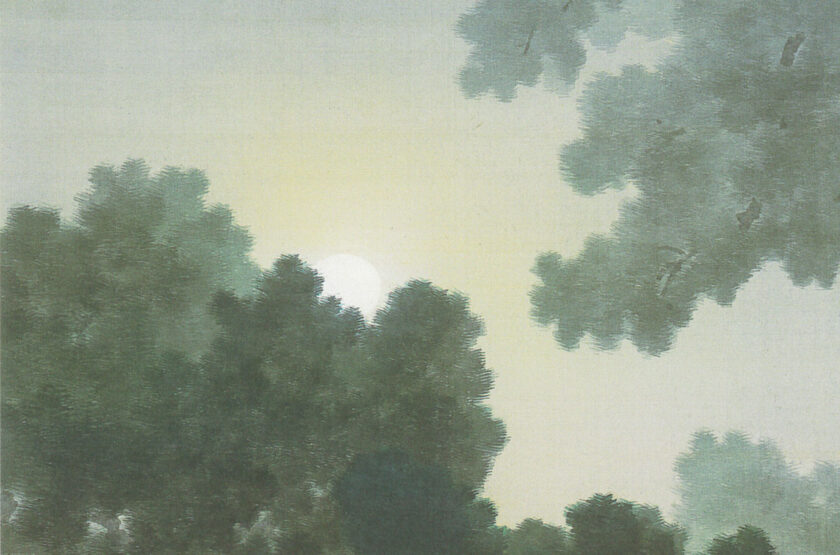 [ 前編 ]意志を越えた導き
[ 前編 ]意志を越えた導き -
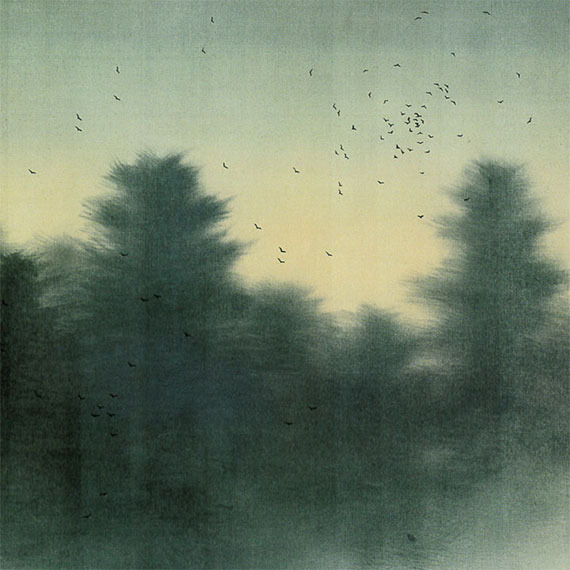 [ 中編 ]新たな光を宿して
[ 中編 ]新たな光を宿して -
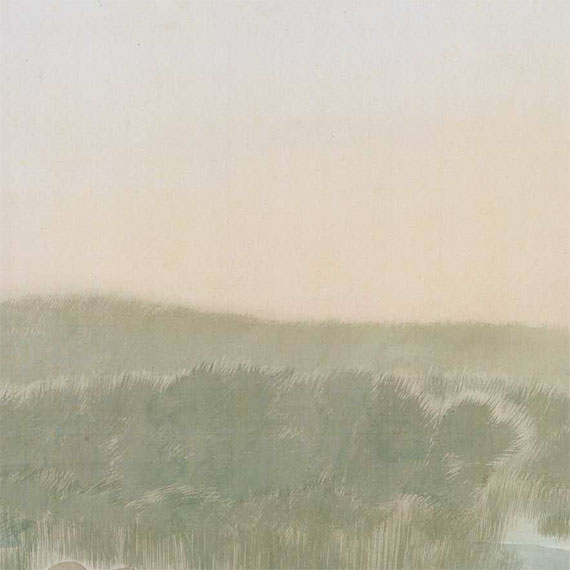 [ 後編 ]運命を変える旅路
[ 後編 ]運命を変える旅路 -
 [ 最終編 ]遥かな光の先に
[ 最終編 ]遥かな光の先に
Hishida
Shunso
Shunso
- text HAS
Reference :
-
「菱田春草」
- 著者:
- 近藤 啓太郎
- 出版:
- 講談社
-
「不熟の天才画家」
- 監修:
- 鶴見香織
- 出版:
- 平凡社
-
「菱田春草 生涯と作品」
- 著者:
- 鶴見香織
- 監修:
- 尾崎正明
- 出版:
- 東京美術
Feature :
-
text :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about