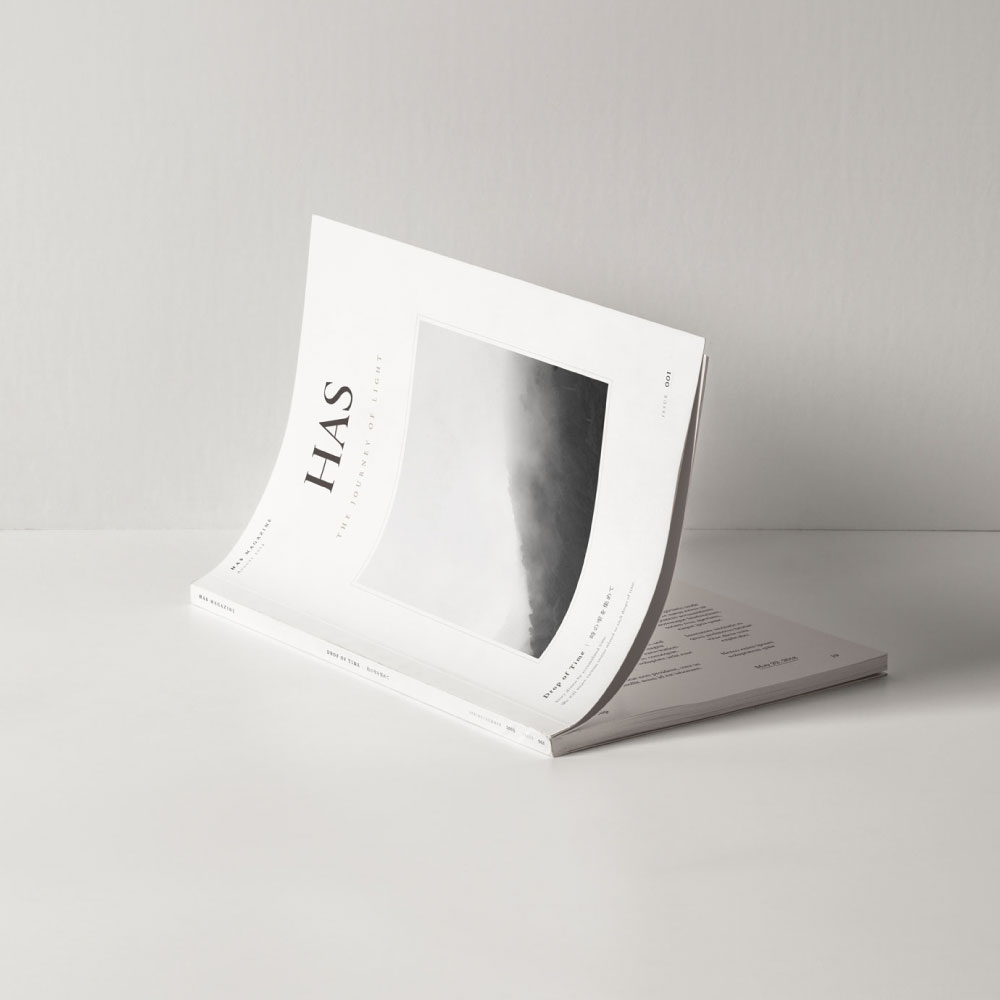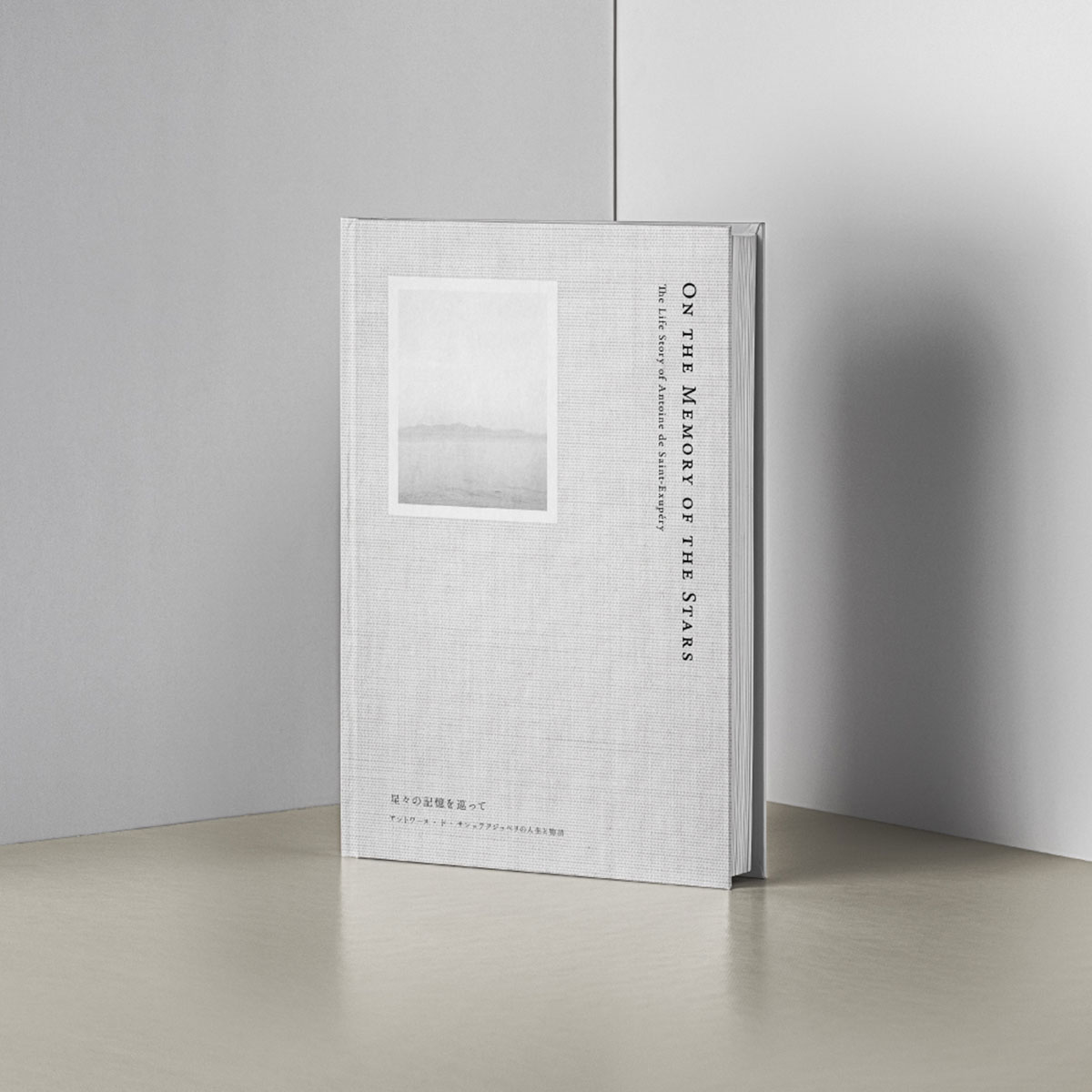さざなみの記憶と滋賀の祈り
Shiga

Shiga
この土地は、そんな豊かな自然に導かれるように、古の時代から数々の物語が紡がれて来た。
そんなこの地に息づく物語に耳を澄ましてゆくと、ある途方もない祈りの言葉に辿り着いた。
その祈りの言葉は、遥かなる創造力の源泉となり、不朽の名作「銀河鉄道の夜」を生んだ、日本を代表する作家・宮沢賢治にも大きな影響を与えたとも言われている。
滋賀の地に息づく様々な物語を辿りながら、途方もない祈りの言葉を紐解いてゆく「さざなみの記憶と滋賀の祈り」。
後編の題名は「さざなみに耳を澄まして」。
最終編となる今回の物語では、中国、そして滋賀の地の古の歴史を辿りながら、途方もない祈り言葉が育まれた理由を紐解いてゆく。
- text / photo HAS
-
 [ 序章 ]夕日に染まる湖
[ 序章 ]夕日に染まる湖 -
 [ 前編 ]ある一冊の本
[ 前編 ]ある一冊の本 -
 [ 中編 ]光の記憶
[ 中編 ]光の記憶 -
 [ 後編 ]さざなみに耳を澄まして
[ 後編 ]さざなみに耳を澄まして
ripples
ripples

祈りの故郷を辿る
神秘の山
宮沢賢治と最澄の創造の光となった一冊の本から育まれた途方もない祈り。
その祈りは、世界の中で唯一日本・滋賀の地において大きく育まれていった。
その事実が投げかける、ひとつの疑問。
なぜそのような途方もない祈りが滋賀の地で育まれたのかということ。
そして、その疑問を紐解く鍵は、天台宗発祥の地・中国の天台山と滋賀が古の時代から育んだ風土の中に隠されていた。
天台宗発祥の地、中国・天台山は、古の時代から神が宿る霊山として、「神の作った風光明媚な場所」と人々に讃えられるほどの聖地であったという。
後に本格的な天台宗を学ぶために、日本から最澄がこの地を訪れるのだが、この山は、古くから道教の聖地としても信仰を集めた場所だった。

道教とは、儒教・仏教に加えて、中国の三大宗教の一つ。
今から遡ること2500年程前の中国で、哲学者・老子を開祖に生まれた教え。
その教えは、自然との調和の中にこそ、人々の本当の安らぎがあることを語っていた。
万物の根源であり、宇宙を形作る究極の真理「道(タオ)」を教えの根幹とし、「無為自然」であることを説いた。
- text / photo HAS
Reference :
-
「図説・滋賀県の歴史」
- 編集:
- 木村 至宏
- 出版:
- 河出書房新社
-
「琵琶湖 - その呼称の由来」
- 著者:
- 木村 至宏
- 出版:
- サンライズ出版
-
「京滋びわ湖山河物語」
- 著者:
- 沢 潔
- 出版:
- 文理閣
-
「近江古代史への招待」
- 著者:
- 松浦 俊和
- 出版:
- 京都新聞出版センター
-
「人類哲学序説」
- 著者:
- 梅原 猛
- 出版:
- 岩波新書
-
「最澄 - 京都・宗祖の旅」
- 著者:
- 百瀬 明治
- 出版:
- 淡交社
-
「鎌倉仏教」
- 著者:
- 平岡 聡
- 出版:
- 角川選書
-
「滋賀県の百年」
- 著者:
- 傳田 功
- 出版:
- 山川出版社
-
「老子」
- 翻訳:
- 小川 環樹
- 出版:
- 中央公論新社
-
「銀河鉄道の夜」
- 著者:
- 宮沢賢治
- 出版:
- 青空文庫
-
「セロ弾きのゴーシュ」
- 著者:
- 宮沢賢治
- 出版:
- 青空文庫
-
text / photo :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about
-
 [ 序章 ]夕日に染まる湖
[ 序章 ]夕日に染まる湖 -
 [ 前編 ]ある一冊の本
[ 前編 ]ある一冊の本 -
 [ 中編 ]光の記憶
[ 中編 ]光の記憶 -
 [ 後編 ]さざなみに耳を澄まして
[ 後編 ]さざなみに耳を澄まして