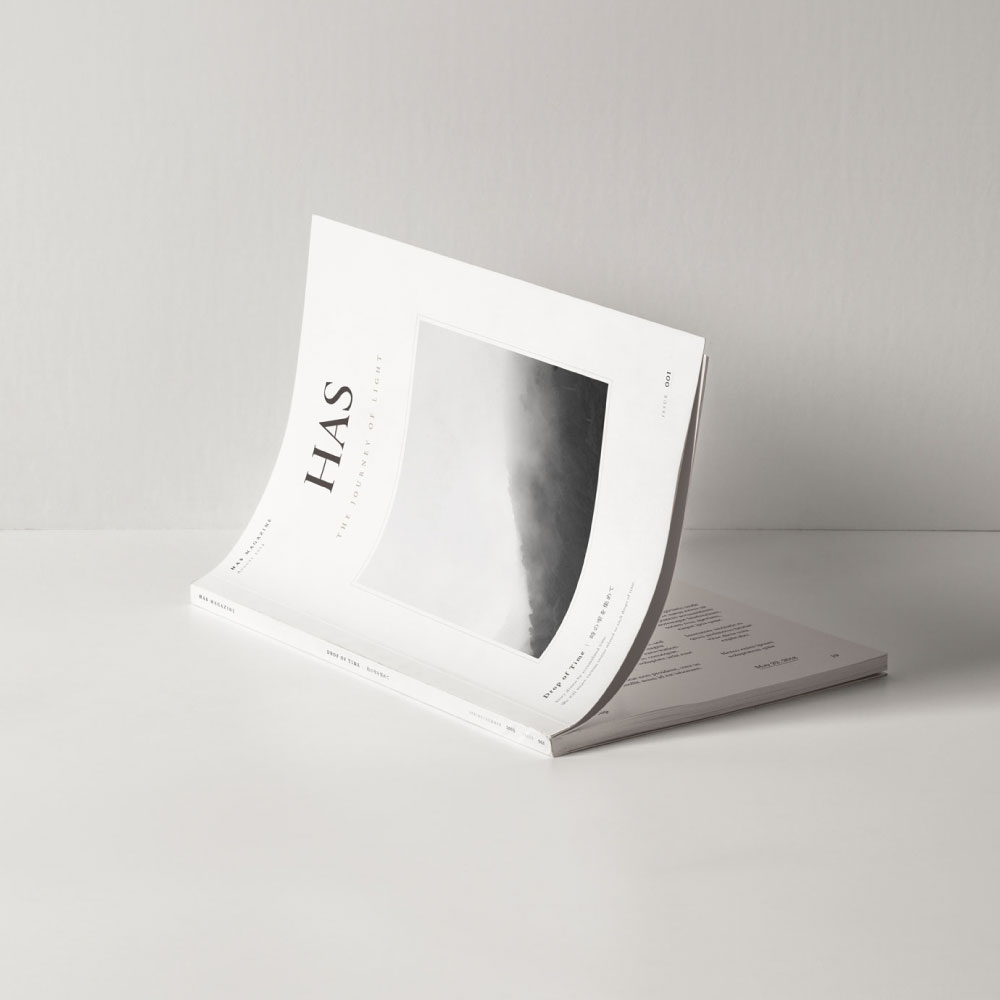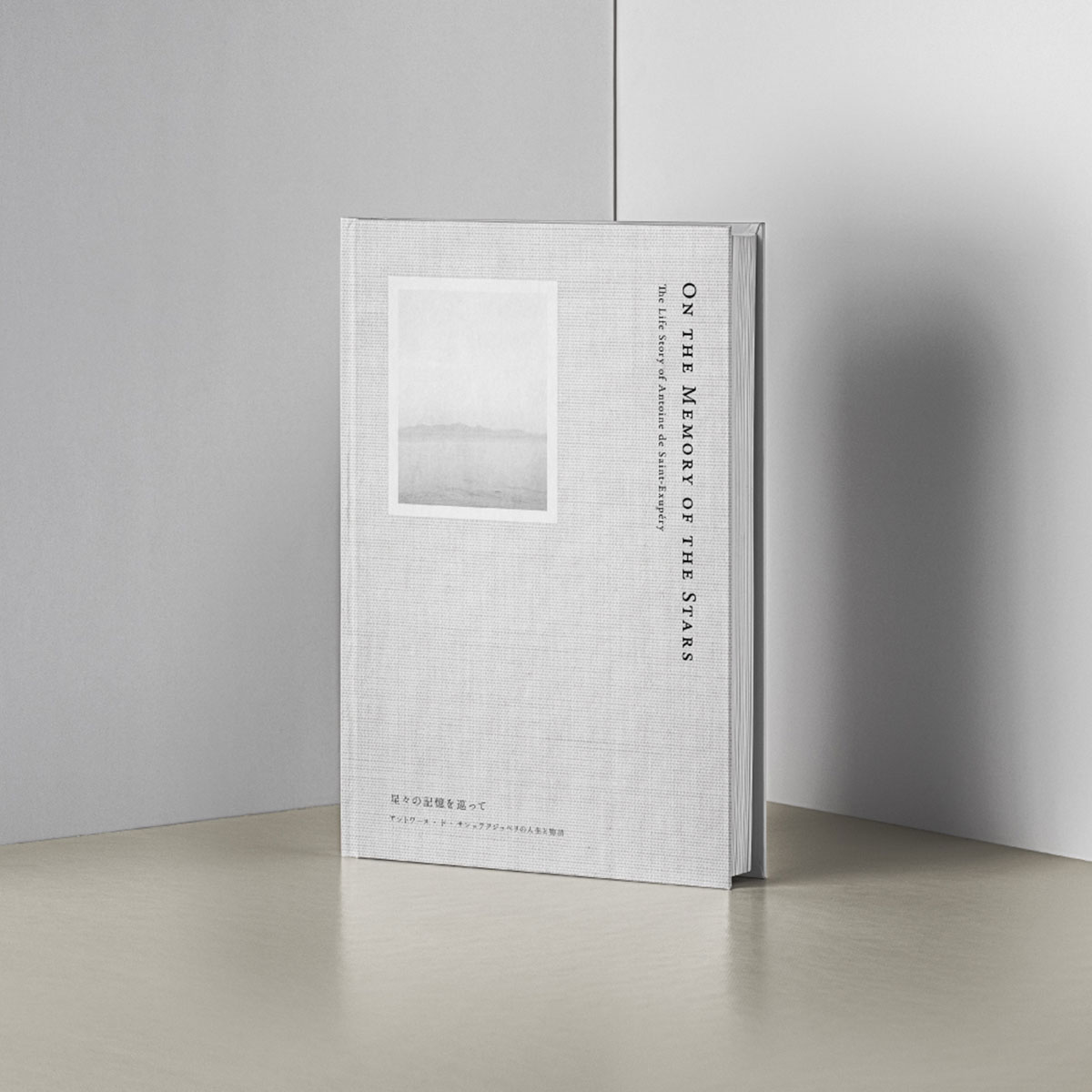京都・宮川神社と亡き姫の物語
Shrine

Shrine
そんな亀岡市内にある小さな町、宮前町の町外れには、山の麓の森に抱かれながら静かに古の時を刻み続ける神社がある。
その神社の名前は、宮川神社。
この神社に流れる物語に耳を澄ましてゆくと、ある一人の亡き姫の物語に出会った。
それは数奇な運命の巡り合わせに翻弄されながらも、ひたむきに自らを生きた一人の女性の物語だった。
そんな亡き姫の物語を紐解きながら、彼女が紡いだ聖なる縁の記憶を辿ってゆく「京都・宮川神社と亡き姫の物語」。
前編の題名は「丹色の波音」。
今回の物語では、宮川神社がある、亀岡の古の物語を紐解きながら、かつてこの地で暮らした亡き姫の姿を明らかにしてゆきたい。
- text / photo HAS
-
 [ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ
[ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ -
 [ 前編 ]丹色の波音
[ 前編 ]丹色の波音 -
 [ 中編 ]たなびく雲の旅路
[ 中編 ]たなびく雲の旅路 -
 [ 後編 ]響き合う縁
[ 後編 ]響き合う縁
Wave
Wave

古の信仰が宿る場所
京都・宮川神社に宿る、亡き姫の物語。
その物語を紐解いてゆくために、まずは宮川神社の古の記憶を辿るところから、この物語を始めてゆきたい。
宮川神社が位置する亀岡市は、その昔「丹波国」という名で呼ばれていた。
この地の歴史は古く、2000年以上もの昔から中国大陸と往来があり、独特の文化を育んでいたという。
その事実を証明するように亀岡市内には、幾つもの磐座(いわくら)を祀る神社が存在する。
磐座とは、古代の人々が信仰の対象とした巨大な岩や石のこと。
かつて人々は、自然物そのものに神を見出し、祈りを捧げていた。
それは、外来の宗教の影響を受ける以前の日本固有の神道「古神道」とも呼ばれる、原始宗教のひとつの信仰のかたちだった。

「古神道」の本質は、自然崇拝にあると言われている。
自然崇拝とは、あらゆる自然物の中に、神が宿るという信仰。
山も海も、草花も、川も、風も、太陽も月も、夜空に瞬く星々も、その内には、それぞれの神が宿っているのだと。
古神道の起源は、明らかではないが一説には、縄文時代まで遡るとも言われている。
縄文時代は、今から遡ること約1万3000年ほど前から約2300年ほど前まで続いた時代のこと。
つまり、そんな古神道の流れを汲む磐座を持つ神社の多くは、必然的に数千年以上の歴史を持っていることになる。
そして、この宮川神社もまた古来から磐座を祀る神社だった。
実際に本殿の裏には、今もなお天を仰ぐほどの巨大な岩が祀られている。

さらに宮川神社は、「延喜式内社(えんぎしきないしゃ)」の神社でもある。
「延喜式内社」とは、「延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)」という台帳に記載された神社のこと。
「延喜式神名帳」とは、今から遡ること約1100年前の平安時代中期に、当時の日本全国の神社を記録した台帳である。
つまり、「延喜式内社」の神社は、少なくとも1100年以上の歴史を持っていることになる。
そうした様々な事実に目を向けてゆくと、この神社がいかに長い時の流れを秘めた神社であるかを感じられるのではないだろうか。

創建の記憶を辿って
そんな様々な歴史的な事実が伝えるように、宮川神社の創建は、遥か古の時代に遡る。
それは今から遡ること約1300年ほど前。
時代は、奈良時代。奈良に都・平城京が置かれていた時のこと。
西暦701年から704年の間に創建されたと伝えられている。
奈良の都を守護し、繁栄を祈るために建てられた春日大社の創建が西暦768年。
春日大社は、私たちにとっても馴染み深い、悠久の歴史を持つ古社のひとつだと言えるだろう。
それに対して、宮川神社は、春日大社の創建より60年も前には既に創建されていたのだ。
そうした事実からも、宮川神社の持つ、長い歴史を知ることが出来る。

現在の宮川神社で祀られる神は、「伊賀古夜姫命(いがこやひめのみこと)と表記」と「誉田別命(ほんだわけのみこと)」の二人の神々。
その内の一神である、「誉田別命」は、創建から時を経て、九州・大分の八幡信仰の総本社・宇佐八幡宮から迎え入れられた神。
そのため、宮川神社の創建当時には祀られていなかった。
宮川神社の創建の起源となったのは、もう一人の「伊賀古夜姫命」と呼ばれる神だった。
この神社が位置する神野山(現在は神尾山と呼ばれる)の山頂に、その神を鎮めたことが起源と伝えられているのだ。
「伊賀古夜姫命」は、その名前に姫という言葉が付く通り、女性の神である。
宮川神社は、遥か古の時代より一人の女神を祀って来た神社なのだ。

その女神は、丹波国を守る国神として古の時代から丹波の地に暮らす人々の間で信仰を集めて来た。
日本において神は、それぞれの神によって様々な系譜を持っている。
時に自然そのものに神を見出すこともあれば、動物の中に神を見出す場合もある。
しかし、宮川神社の「伊賀古夜姫命(以降、【伊賀古夜姫】と表記)」は、そのどちらでもない。
彼女は、この地で神として神格化される以前、この地で暮らした一人の女性だったのだ。
なぜ一人の女性だった彼女が多くの人々の信仰を集める神として信仰を集めてゆくことになったのだろうか。
その答えは、この地に残された物語と失われたある書物に残された物語の中に隠されていたのだ。
そして、それぞれの物語の中には、宮川神社から始まる聖なる縁を紐解く鍵もまた隠されていたのだ。

亡き姫の記憶
宮川神社が位置する亀岡市宮前町には、ひとつの物語が残されている。
それは、ある一族が辿った物語。
物語の舞台は、彼らが暮らした「丹波国」。
かつて亀岡市は、「丹波国」と呼ばれる国の一部だった。
古くから豊穣の大地として知られたこの土地は、稲作が盛んに行われていた。
収穫期には、「赤米」と呼ばれる赤褐色の稲穂が平野一面に広がるほどだったという。
「赤米」とは、縄文時代に日本に最初に伝わった稲の一種。
またの名を「古代米」とも言う。

収穫期に、この地を訪れた人々は、その風景を目にして「まるで丹色の波がたなびいているようだ」と口々に語ったという。
そんな人々が想い描いた情景から「丹波」という土地の名前が付けられたと伝えられている。
「丹波」の由来は諸説あるのだが、そのひとつには、そんな実り豊かな大地の記憶が流れているのだ。
この物語に登場する一族も、そんな豊かな大地に支えられ、平和で豊かな暮らしを送っていたのだろう。
そして、その一族の長には、ある一人の娘がいた。

その娘の名前は、「伊賀古夜姫」。
そう、その族長の娘こそ、のちに宮川神社の女神として祀られる一人の女性だったのだ。
彼女は、かつてある一族の姫君として丹波の地で暮らしていたのだ。
豊かな土地で暮らす一族の姫君だった彼女は、きっと幼い頃から何不自由ない豊かな暮らしを送っていたのかもしれない。
だがしかし、その暮らしはいつまでも続くことはなかった。
後に彼女は、その一族が辿った運命に巻き込まれてゆくことになるのだ。
- text / photo HAS
Reference :
-
「宮前町のしおり(2019年作成)」
- 発行:
- 宮前町自治会
-
「丹波物語」
- 出版:
- 国書刊行会
- 著者:
- 麻井 玖美、角田 直美
-
「出雲大神宮史 : 丹波國一之宮」
- 出版:
- 出雲大神宮社殿創建千三百年大祭記念事業奉賛会
- 著者:
- 上田正昭 監修・編纂委員長
- 編集:
- 出雲大神宮史編纂委員会
-
text / photo :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about
-
 [ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ
[ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ -
 [ 前編 ]丹色の波音
[ 前編 ]丹色の波音 -
 [ 中編 ]たなびく雲の旅路
[ 中編 ]たなびく雲の旅路 -
 [ 後編 ]響き合う縁
[ 後編 ]響き合う縁