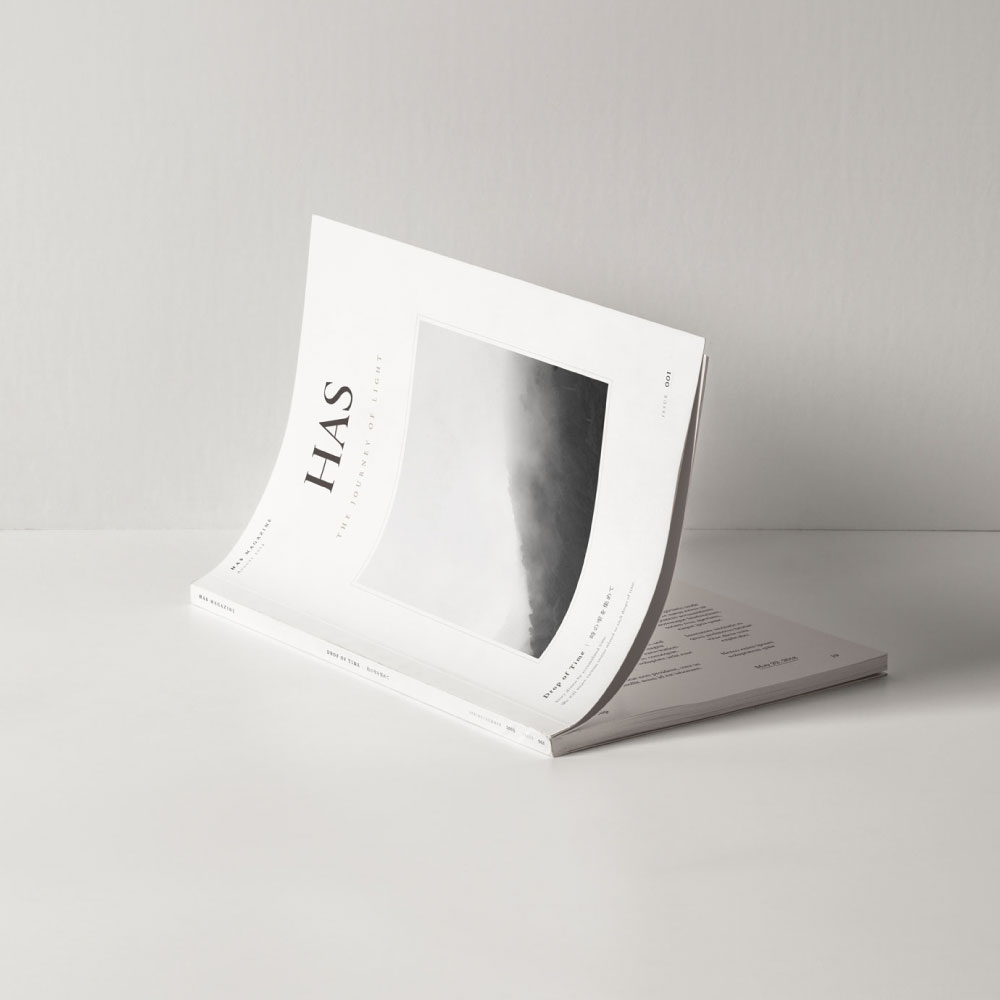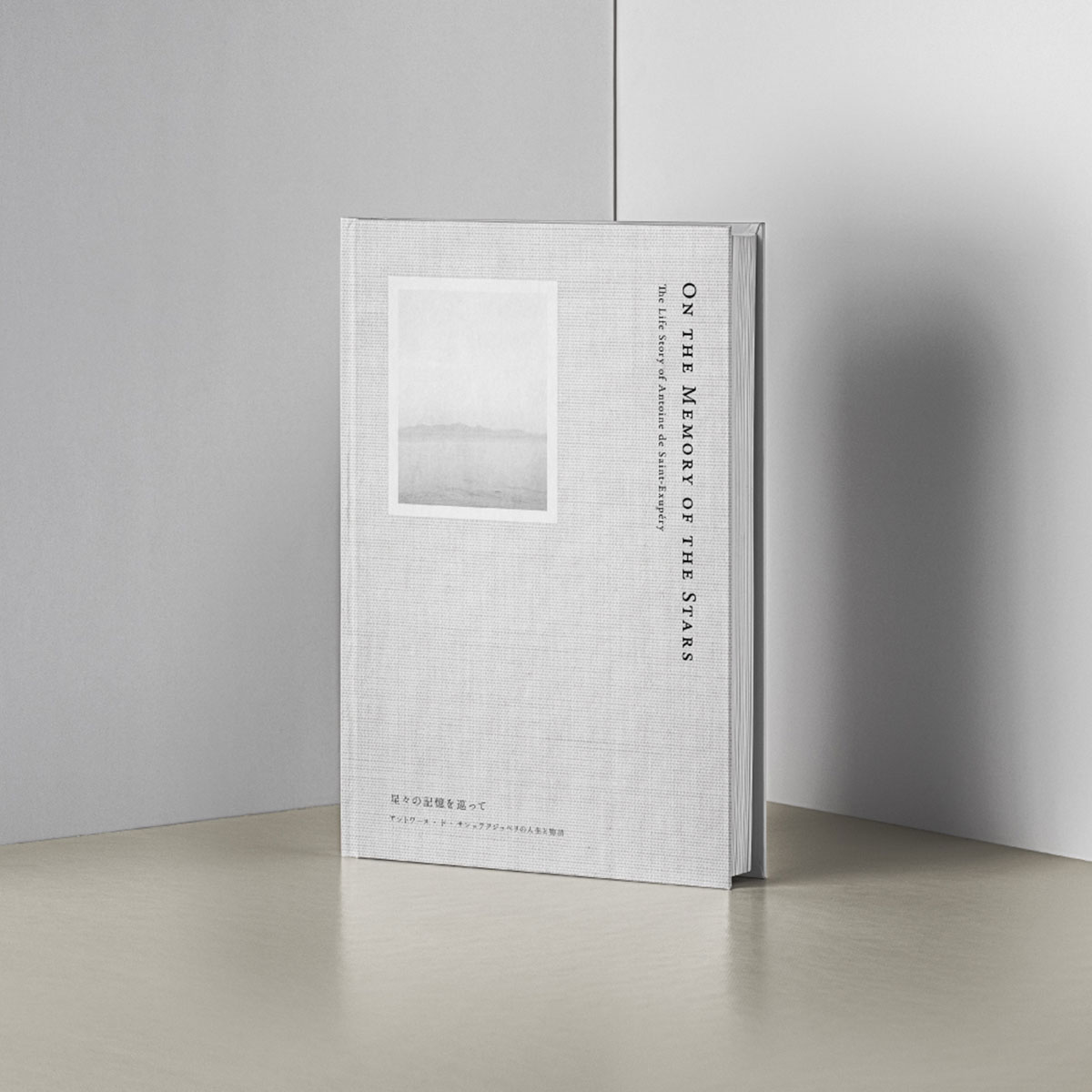[ 全4話 ]
奈良・春日野と
聖なる森の月夜
聖なる森の月夜
Sacred Forest
in Nara
in Nara
Sacred Forest
in Nara
in Nara
全4話

Sacred Forest
in Nara
in Nara
古の都・奈良。
この地を訪れると、ふと心に浮かぶあるひとつの歌がある。
「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも」
この歌は、百人一首の中に収められた、あまりに有名な歌のひとつ。
作者は、安倍仲麿(あべのなかまろ)。
彼は、今から遡ること約1300年程前、遣唐使として中国に渡った一人の留学生であった。
だが様々な運命の巡り合わせから日本への帰国を果たすことが出来ず、その生涯を中国の地で終えることになる。
そんな彼が抱き続けた、深い望郷の念を紡いだのがこの歌であった。
ある時、彼が夜空を仰ぎ、遥か彼方を眺めると月が昇っていた。
彼は、その月を眺めながら自らの故郷、奈良・春日野にある三笠山に昇る月と同じ月なのだろうか、と物想いに耽ったという。
そうすることで彼は、海の彼方にある故郷の記憶を手繰り寄せていたのかもしれない。
彼がかつて歌った三笠山とは、奈良・春日大社の後方に今も佇む、御蓋山のこと。この山は、遥か古の時代から神が宿る山と仰がれ、聖地として定められて来たという。
そして、この山の中には、特別な祭祀を除き1100年以上もの昔から入山を禁止されて来た聖なる森がある。
その森の名は「春日山原始林」。
太古の自然を今に残す貴重な森として、世界遺産にも登録されている森だ。
そんな遥かなる時を宿す、聖なる森の記憶を辿ってゆくと、あるひとつの記憶に辿り着いた。
それは、かつて古の人々が紡いだ人と自然の共生の記憶。
その記憶は、様々な環境問題に直面する、今の地球に生きる全ての人々にとって指針になりうる大いなる記憶であった。
古の都・奈良に息づく、聖なる森の物語を紐解きながら、「春日山原始林」に宿る古の共生の記憶を辿ってゆきたい。
この地を訪れると、ふと心に浮かぶあるひとつの歌がある。
「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも」
この歌は、百人一首の中に収められた、あまりに有名な歌のひとつ。
作者は、安倍仲麿(あべのなかまろ)。
彼は、今から遡ること約1300年程前、遣唐使として中国に渡った一人の留学生であった。
だが様々な運命の巡り合わせから日本への帰国を果たすことが出来ず、その生涯を中国の地で終えることになる。
そんな彼が抱き続けた、深い望郷の念を紡いだのがこの歌であった。
ある時、彼が夜空を仰ぎ、遥か彼方を眺めると月が昇っていた。
彼は、その月を眺めながら自らの故郷、奈良・春日野にある三笠山に昇る月と同じ月なのだろうか、と物想いに耽ったという。
そうすることで彼は、海の彼方にある故郷の記憶を手繰り寄せていたのかもしれない。
彼がかつて歌った三笠山とは、奈良・春日大社の後方に今も佇む、御蓋山のこと。この山は、遥か古の時代から神が宿る山と仰がれ、聖地として定められて来たという。
そして、この山の中には、特別な祭祀を除き1100年以上もの昔から入山を禁止されて来た聖なる森がある。
その森の名は「春日山原始林」。
太古の自然を今に残す貴重な森として、世界遺産にも登録されている森だ。
そんな遥かなる時を宿す、聖なる森の記憶を辿ってゆくと、あるひとつの記憶に辿り着いた。
それは、かつて古の人々が紡いだ人と自然の共生の記憶。
その記憶は、様々な環境問題に直面する、今の地球に生きる全ての人々にとって指針になりうる大いなる記憶であった。
古の都・奈良に息づく、聖なる森の物語を紐解きながら、「春日山原始林」に宿る古の共生の記憶を辿ってゆきたい。
- text / photo HAS

Chapter list
-
 [ 序章 ]彼方の月夜を眺めて
[ 序章 ]彼方の月夜を眺めて -
 [ 前編 ]聖なる森の記憶
[ 前編 ]聖なる森の記憶 -
 [ 中編 ]煌びやかな文明の影
[ 中編 ]煌びやかな文明の影 -
 [ 後編 ]無窮に繋がる生命
[ 後編 ]無窮に繋がる生命 -
 [ 最終編 ]世界を繋ぐ森の記憶
[ 最終編 ]世界を繋ぐ森の記憶
Sacred Forest
in Nara
in Nara
- text / photo HAS
Reference :
-
「日本という国―歴史と人間の再発見」
- 編集:
- 梅原猛
- 編集:
- 上田正昭
- 出版:
- 大和書房
-
「森の日本文化 - 縄文から未来へ」
- 著者:
- 安田喜憲
- 出版:
- 新思索社
-
「鎮守の森 - 社叢学への招待」
- 著者:
- 上田正昭
- 出版:
- 平凡社
-
「照葉樹林文化 - 日本文化の深層」
- 編集:
- 上山 春平
- 出版:
- 中央公論新社
-
「照葉樹林文化論の現代的展開」
- 著者/編集:
- 金子 務
- 著者/編集:
- 山口 裕文
-
「世界遺産 春日山原始林 -照葉樹林とシカをめぐる生態と文化-」
- 編集:
- 前迫ゆり
- 出版:
- ナカニシヤ出版
-
「鎮守の森の物語 - もうひとつの都市の緑」
- 著者:
- 上田 篤
-
「照葉樹林文化の成立と現在」
- 著者:
- 田畑 久夫
- 出版:
- 古今書院
-
「神道千年のいのり 春日大社の心」
- 著者:
- 花山院弘匡
- 出版:
- 春秋社
-
「宮司が語る御由緒三十話 - 春日大社のすべて」
- 著者:
- 花山院弘匡
- 出版:
- 中央公論新社
-
「長い旅の途上」
- 著者:
- 星野道夫
- 出版:
- 文藝春秋
Feature :
-
text / photo :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about