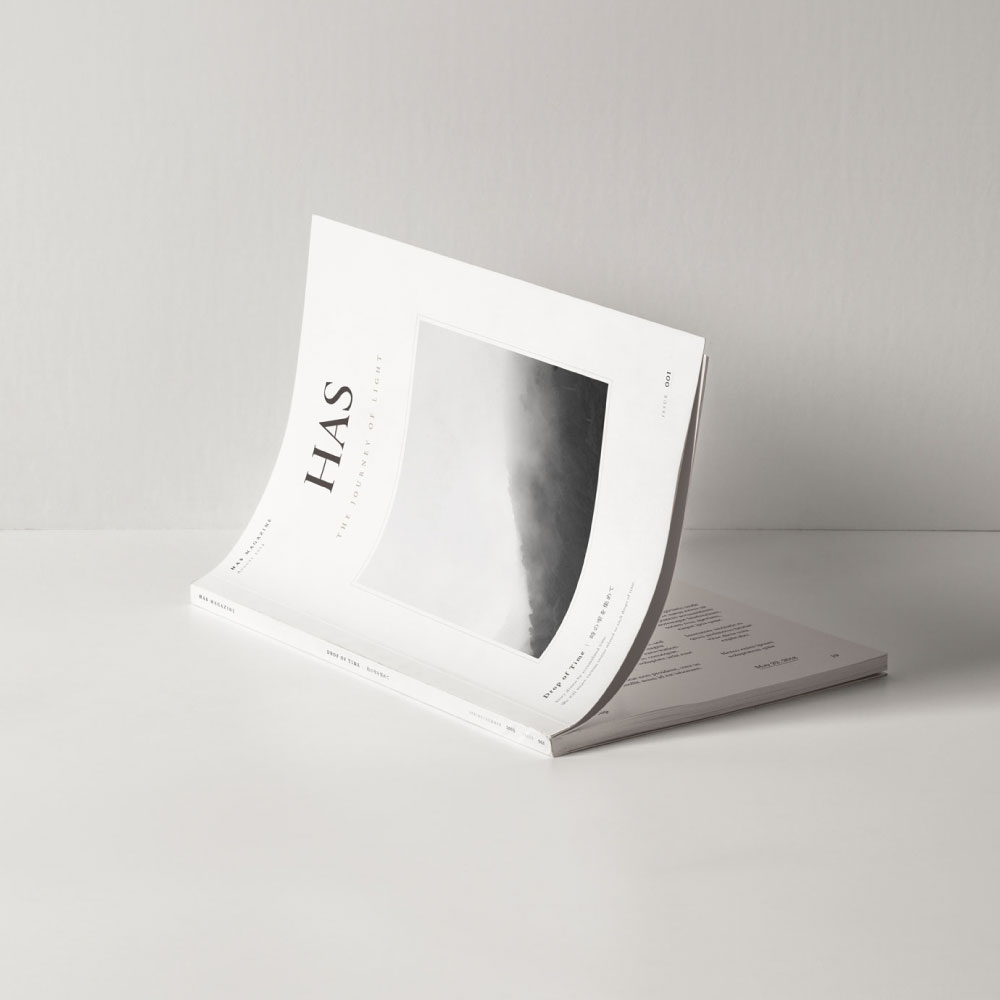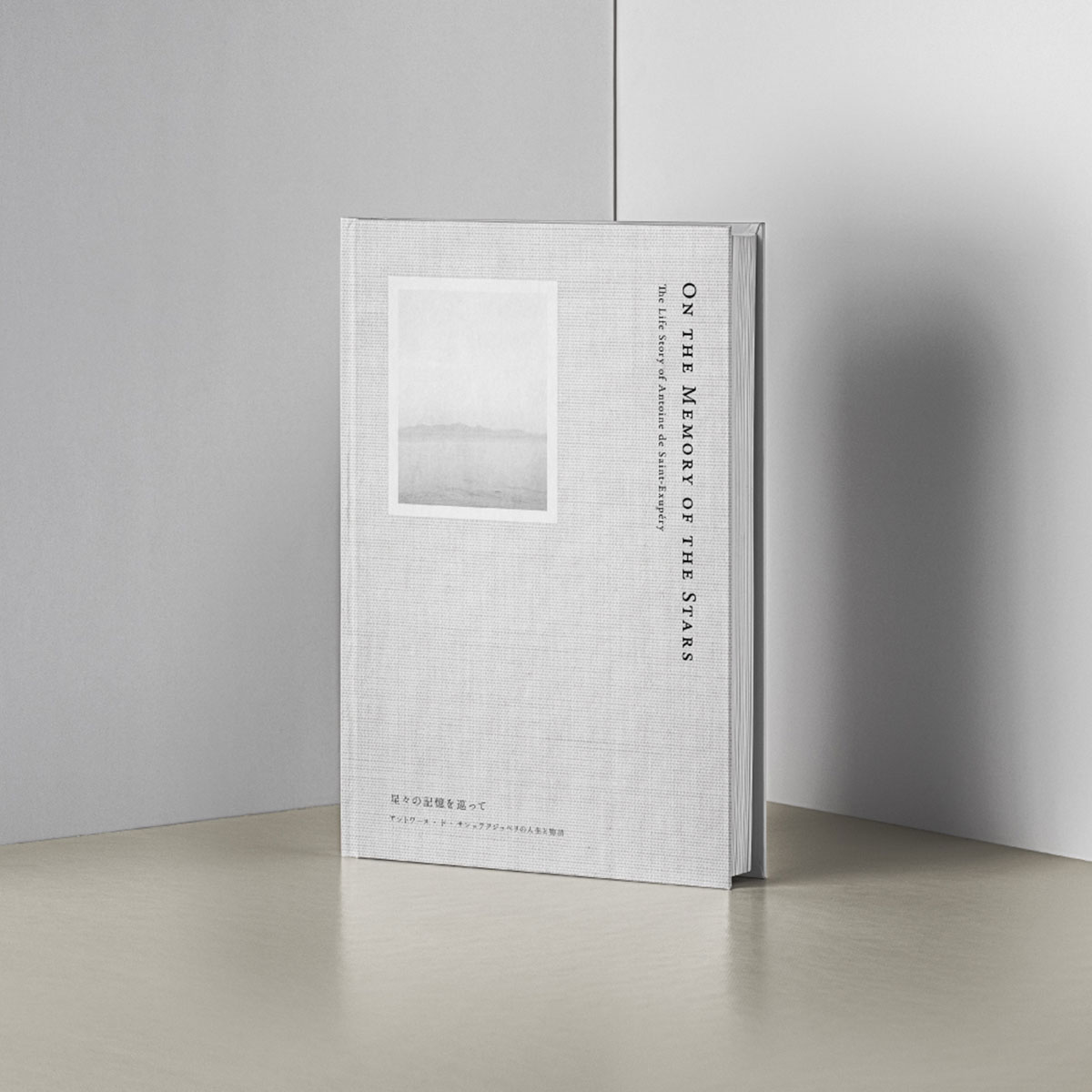唐招提寺と幾重もの旅路
Story

Story
古の都・平城京の西の端に位置したこの場所には、千年もの時を越え、今なお人々を惹きつけてやまない、ある寺院がある。
その寺院の名は、唐招提寺。
かつて中国の地から、正統な仏教を伝来するために幾つもの苦難を乗り越え、日本に辿り着いた僧・鑑真によって創建された。
そんな唐招提寺に宿る、一人の僧侶の物語と交錯する様々な人々の歩みに耳を傾けながら、幾つもの旅の物語を辿ってゆく、「唐招提寺と幾重もの旅路」。
前編の題名は、「唐招提寺に至る旅へ」。
今回の物語では、僧侶・鑑真の記憶を紐解きながら、彼の辿った足跡と日本へと至る旅の物語を紡いでゆきたい。
- Text / Photo HAS
-
 [ 序章 ]唐招提寺と幾重もの旅路
[ 序章 ]唐招提寺と幾重もの旅路 -
 [ 前編 ]唐招提寺に至る旅へ
[ 前編 ]唐招提寺に至る旅へ -
 [ 後編 ]唐招提寺から始まる旅へ
[ 後編 ]唐招提寺から始まる旅へ
Toshodaiji
Toshodaiji

旅のはじまり
一人の少年の物語
この旅の物語は、たった一人の少年から始まる。
彼の名は、淳于と言った。
その少年は、遡ること約1300年前、中国・揚州のとある港町に生まれた。
熱心な仏教信者である父のもとに生まれ、生家には幼い頃より仏教的で穏やかな空気が漂っていたという。
その一方で彼が生まれ育った港町は、様々な人々が往来する、中国南方では有数の活気溢れる地方都市であった。

運河を利用した交通の要衝として繁栄し、訪れる人種も様々。
はるかシルクロードを越え、インドやイランといった多様な国々の人々が訪れ、さらには大海原を越え、中国を訪れる日本人も往来する、国際都市でもあったのだ。
彼は、そうした環境の中で育っていった。
その中で彼は、一体何を感じ、何を思ったのだろうか。
想像することしか出来ないが、自然と世界を見渡す国際的な感性と仏教への理解を幼い頃より深めていたのではないだろうか。
もちろん、彼自身がいつの日か遥か遠い異国の地で、鑑真という名の僧侶として、その身を埋めることになるとは想像するはずもなく。

運命の出会い
彼が14歳になった時、ある運命の出会いを果たす。
それは大いなる旅の始まりの一歩となる出会いだった。
ある日、彼は父に連れられ、とある寺院に参拝する。
その寺院の中で、ある仏像に出会ったのだ。
その仏像に強い感銘を受けた彼は、その瞬間に直感に導かれるように、ある一つの決意を抱く。
それは出家をし、僧として生きてゆくという決意だった。
なんと彼は、その場で父にその想いを伝え、僧の道に進むことを願ったというのだ。

まだまだあどけなさが残る年齢である。
とても普通の少年に出来る決断ではないだろう。
この決断の中に、ただ者ではない何か。何かいずれ大きなことを成し遂げるであろう偉人の片鱗が感じられるのではないだろうか。
そうして彼は、僧としての長い、長い道程を歩み始めることになる。
そして、この決断が後に、彼自身を遥か異国の日本の地、奈良・唐招提寺に至る旅へと導いてゆくことになるのである。

望郷と異国の地へ
その後、鑑真は、仏教者としての学びを深めてゆく。
そして、その学びが深まるにつれ、彼の学び得た境地から教えを受けるために、多くの人々が彼のもとに集うようになっていた。
気が付けば、彼の弟子は、約4万人にものぼっていたという。
彼の出身地である揚州だけでなく、中国各地にも門下生を抱えるようになっていた。
鑑真、この時46歳。
彼が僧の道を志してから、30年以上もの歳月が過ぎていた。
もちろん様々な苦労はあっただろうが、順風満帆とも言える日々を送っていた。
そんな日々を過ごす中で、ある日突然二人の青年が鑑真のもとを訪れる。
彼らは、大海原を越え、日本の地から中国の地に辿り着いた若者であった。
二人の名は、普照と栄叡と言った。
彼らは、仏教の教えを正しく伝授出来る僧を日本に招聘するために、遣唐使として派遣されていたのだ。

現代のような造船技術や航海術が確立していない当時、遣唐使として日本から中国への航海は、困難を極めていた。
無事に帰還できる割合は、全体の約6割程度。
航海に出た約半数もの人々が命を落とす、まさに命懸けの旅だったのだ。
たとえ無事に中国の地に辿り着くことが出来でも、帰国の船で遭難してしまうこともある。
二度と祖国の地を踏むことが出来ないかもしれない。
望郷の想いは絶えず、二人の胸を締め付けただろう。
だがしかし、異国の地で新たな学びを得るために、そして日本に規範となるべき偉大な僧を招聘するために、彼らは旅に出たのだった。
その後、幸運にも中国の地に辿り着くことが出来た二人は、9年もの学びを経て、ついに鑑真と出会うことになる。
そして、必然の縁に導かれるように、それぞれの旅路が交錯する時、ついに大いなる物語が動き始めてゆくのである。

交錯する旅路
意志を越えた出会い
普照と栄叡が、中国から日本へ僧の招聘を依頼するために、鑑真のもとを訪れた時、鑑真は弟子に向かってこう語りかけたという。
「この中に仏法を伝えに日本へ行く者はいないか」と。
しかし、無事に着くかどうかも分からない命懸けの旅。
ましてや日本という未知の異国の地へと向かう旅である。
誰もが黙ったまま、その問いに答えなかった。
そんな弟子たちの反応に対し、悩む間もなく鑑真は、こう静かに語ったという。
「これは仏のためで、命を惜しむことではない。私が行くだけだ。」と。
なんと鑑真自らが日本へ向かうことを決めたのだ。

二人は、あろうことか鑑真自らが来日を決意するとは、想像だにしていなかった。
なぜなら彼らは、鑑真に対し、門下生の誰かを日本にお連れしたいとだけ伝えていたからだ。
何より一番驚いたのは、依頼に訪れた二人だったのかもしれない。
鑑真の持つ、人並外れた感性が自らの宿命を直感的に感じ取ったのか。
それとも自らの命を賭し、鑑真のもとを訪れた、二人の中にただならぬ情熱を感じ取ったのか。
その決断に至る想いは、今では誰も知ることは出来ない。

後に唐招提寺の障壁画を描いた画家・東山魁夷は、自身の本の中で、この時の鑑真の決断についてこう語っている。
「超人的な業を成し得た人は、むしろ、自己の意志に頼らなかった人が多いのではないだろうか。人間の意志の限界を知っていて、それよりも遥かに大きなものに身を任せたと考えないではいられない。」
(著者 : 東山魁夷『唐招提寺への道』 新潮社より )
まさに意志を越えた何かに導かれるようにして、鑑真は、新たな旅路へと向かっていったのである。

喪失と悲願を抱きながら
運命とは不思議なものである。
様々な偶然が重なり合うように導かれたその旅路は、決して簡単な道のりではなかった。
運命そのものが、その運命自体のありようを問うかのように、幾度もの試練を与えたのだ。
度重なる航海の失敗が続き、日本への旅は未だ実現していなかった。
なんと5度もの渡航の失敗に見舞われていたのだ。
渡航を決意してから、12年もの歳月が過ぎようとしていた。
時に仲間の密告にあい、時に政府の監視網に見つかり、時に遭難をするという苦難の連続であった。

また、その苦難の日々の中で、数え切れない別れもあった。
ともに日本から中国の地を訪れた普照と栄叡は、まさに運命を共にする無二の親友でもあった。
さらに右も左も分からない異国の地で共に生きた彼らにとって、お互いの存在は無くてはならない家族のようなものだっただろう。
だが、その日々の中で栄叡は、度重なる失敗の中で蓄積された過労の果てに病にかかり、命を落としてしまう。
彼の最期を看取った普照は、その悲しみのあまり我を忘れて号泣したという。

そして、鑑真の愛弟子であった祥彦という僧もその船旅の途中で命を落としてしまう。
不屈の人のような印象を受ける鑑真であるが、この時ばかりは、「彦や、彦や」と弟子の名前を何度も呼びながら悲しみに暮れたという。
さらに苦難は重なり、長旅の苦労と疲労のせいか、鑑真は失明し、光を失ってしまう。
なんという苦しみであろうか。
運命の無常さ、人間の弱さを否応なしに突き付けるような月日であった。
しかし、そうした苦難に見舞われながらも、彼らは決して諦めることはなかったのだ。
そして、ついに6度目の渡航で、悲願の日本への上陸を果たす。
鑑真この時、66歳。
気が付けば、14歳の少年が一つの決意をもとに歩み始めたあの日から、50年もの歳月が流れていたのだった。
- Text / Photo HAS
Information :
-
唐招提寺
address : 奈良県奈良市五条町13−46url : www.toshodaiji.jp
Reference :
-
「鑑真」
- 著者:
- 安藤更生
- 出版:
- 吉川弘文館
-
「唐招提寺への道」
- 著者:
- 東山魁夷
- 出版:
- 新潮社
-
「天平の甍」
- 著者:
- 井上靖
- 出版:
- 新潮社
-
Text / Photo :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about
-
 [ 序章 ]唐招提寺と幾重もの旅路
[ 序章 ]唐招提寺と幾重もの旅路 -
 [ 前編 ]唐招提寺に至る旅へ
[ 前編 ]唐招提寺に至る旅へ -
 [ 後編 ]唐招提寺から始まる旅へ
[ 後編 ]唐招提寺から始まる旅へ