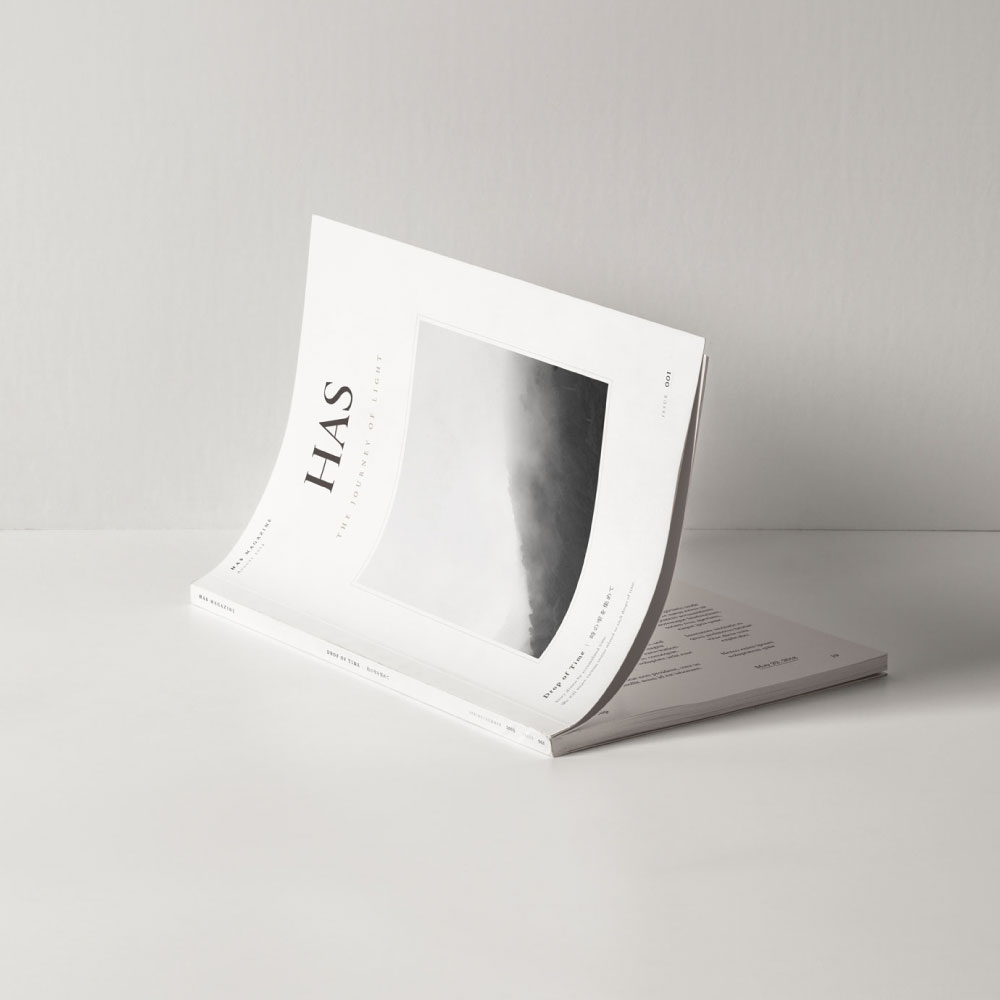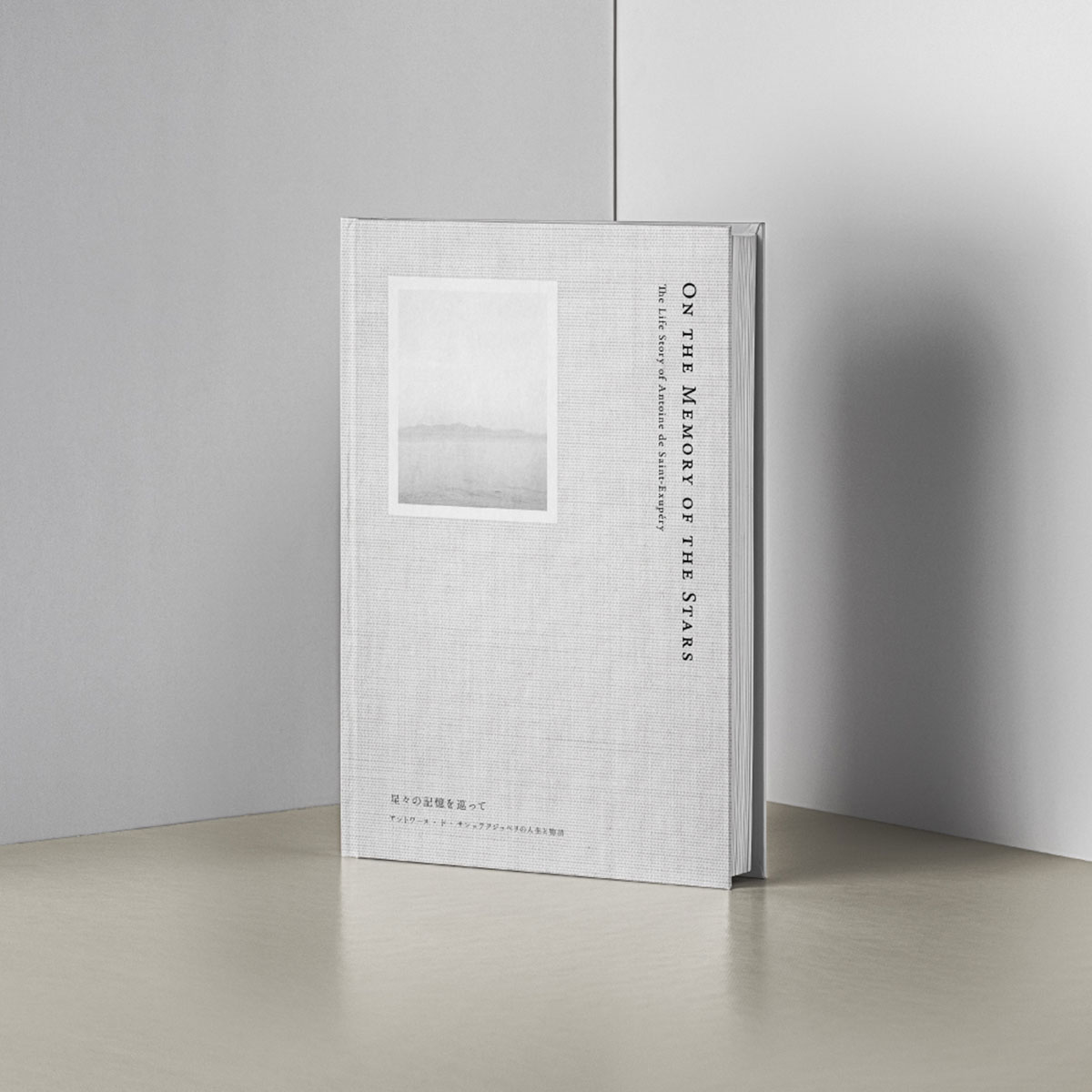京都・宮川神社と亡き姫の物語
Shrine

Shrine
そんな亀岡市内にある小さな町、宮前町の町外れには、山の麓の森に抱かれながら静かに古の時を刻み続ける神社がある。
その神社の名前は、宮川神社。
この神社に流れる物語に耳を澄ましてゆくと、ある一人の亡き姫の物語に出会った。
それは数奇な運命の巡り合わせに翻弄されながらも、ひたむきに自らを生きた一人の女性の物語だった。
そんな亡き姫の物語を紐解きながら、彼女が紡いだ聖なる縁の記憶を辿ってゆく「京都・宮川神社と亡き姫の物語」。
中編の題名は「たなびく雲の旅路」。
今回の物語では、かつて亀岡の地で暮らした亡き姫の一族の記憶を紐解きながら、その一族が辿った運命の物語を辿ってゆきたい。
- text / photo HAS
-
 [ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ
[ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ -
 [ 前編 ]丹色の波音
[ 前編 ]丹色の波音 -
 [ 中編 ]たなびく雲の旅路
[ 中編 ]たなびく雲の旅路 -
 [ 後編 ]響き合う縁
[ 後編 ]響き合う縁
of Clouds
of Clouds

ある一族の記憶
宮川神社が位置する亀岡市宮前町に残されたひとつの物語。
そこには、宮川神社で祀られる女神「伊賀古夜姫(いがこやひめ)」の物語が記されていた。
それは、かつて彼女がある一族の長の娘であった時の物語だった。
そんな彼女が属した一族とは、一体どんな人々だったのだろうか。
その一族にまつわる、ひとつの歌が残されている。
「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を」
これは日本神話に登場する伝説の神、スサノオが愛する妻を想い歌ったと言われる歌。

スサノオは、旅の途中で、ある困り果てて涙を流す老夫婦に出会う。
彼らには八人の娘がいたのだが、毎年近くの山から現れるヤマタノオロチという八つの首を持つ大蛇に一人づつ食べられてしまったという。
残された娘は、あと一人。
今年もヤマタノオロチが現れる時期となり、きっとこの娘も食べられてしまうのだろうと。
その話を聞いたスサノオは、その娘を妻に迎える代わりにヤマタノオロチの退治を約束する。
そして、見事にヤマタノオロチを退治したスサノオは、妻との新居にふさわしい土地を探し求めて旅をする。
その旅の道中で、空の彼方に八色の雲が立ち上がるのを見て、その土地を妻との新居にすることを決める。
妻が安心して暮らせるよう、そんな幾重にも重なる雲のように家のまわりに八重垣を造るのだと。

スサノオが妻との新居として定めた土地は、出雲と呼ばれる土地だった。
その土地は、その歌になぞらえて「八雲立つ出雲」とも讃えられるほど、たなびく雲が幾重にも重なる美しい風景が広がる土地だった。
その土地こそ、彼女の一族が故郷とする土地。
彼らは、そんな故郷の美しい風景を一族の名前とし、自らを出雲族と名乗った。
「伊賀古夜姫」は、遥か昔、山陰地方に存在したと伝えられる「古代出雲の文化」を起源に持つ出雲族の子孫だったのだ。
「古代出雲」は、今から遡ること二千年以上前の弥生時代から古墳時代にかけて、島根県の出雲平野で育まれた文化。

その時代は、日本海側では、九州や朝鮮半島との交易が活発に行われていた。
彼らが暮らす土地には、山陰地方でも随一の港があったという。
それほど大きな力を持つ一族だった。
「出雲」という言葉を聞くと、私たちが真っ先に想い浮かべるのは、現在の島根県
にある「出雲大社」ではないだろうか。
まさにその「出雲大社」こそ、彼らが信仰する神を祀った聖地なのだ。
だが出雲族の起源は、山陰地方、現在の島根県にある。
なぜ故郷の地から遥か遠く離れた、亀岡の地に彼らの子孫が暮らしていたのか不思議に感じられるかもしれない。
しかし、亀岡の地の歴史を紐解いてゆくと、かつてこの地で出雲族の人々が暮らした確かな足跡が残されているのだ。

遥かなる旅路
宮川神社が建つ亀岡盆地には、出雲大神宮と呼ばれる神社がある。
「出雲」という名前が表す通り、この神社は「亀岡」と「出雲族」との関わりの記憶を秘めいている。
この神社の創建の起源は、かつて出雲大神宮が建つ山そのものを、人々が信仰していたことから始まる。
その時代から遡ると、この神社の信仰の歴史は、なんと一万年以上もの長きにわたるという。
そんな長い歴史を持つ出雲大神宮には、亀岡盆地の創成の神話が残されている。
その神話は、太古の時代の亀岡の風土を描くところから始まる。

亀岡盆地が大蛇の棲む丹色の湖だった、太古の昔のこと。
亀岡盆地のとある山に降臨した、出雲の八柱の神々が一艘の木船に乗ってやってきたという。
それからほどなくして、彼らは現在の保津峡にあたる峡谷を鍬や鋤を用いて開削した。
すると亀岡盆地を埋め尽くしていた水は見る見るうちになくなり、現在の京都市内へと流れ込んでいった。
そうして水がなくなった亀岡盆地は、肥沃な大地になったと語られ、この神話は結ばれる。
神話は多くの場合、事実を物語として後世に語り継ぐために、神々の世界を舞台にした壮大な世界観の中で描かれる。

つまりこの伝承は、出雲の神々を祀る、出雲族の人々が、亀岡盆地を開拓した偉業を伝えた物語としても読み解くことが出来るのだ。
それはまた、新たな土地を求め、遥かなる旅を重ねた、出雲族の物語とも言えるかもしれない。
亀岡と出雲という遠く離れた二つの土地は、古の神話を紐解くことで、互いの深い関係性を見出すことが出来るのだ。
「伊賀古夜姫」は、そんな遥かな旅路の先で、新天地で生きた出雲族の一人だったのだ。

落とされた影
遥かなる旅の果てに、湖の開削という大事業を経て、ようやく手にした肥沃の大地。
その土地は後に、「丹波」という土地の由来になるほどの豊穣の大地となった。
かつてこの地で暮らした出雲族にとって、亀岡盆地は多くの先人たちの苦労の先に手にした悲願の地であったかもしれない。
しかし、そんな彼らの豊かな日々に影を落とすように、ある出来事が起きる。
出雲族が暮らした亀岡盆地を舞台に、ある一族との間で勢力争いが勃発したのだ。
その一族は、京都盆地からやってきた一族だった。

その勢力争いの原因は明らかにされてはいない。
しかし、当時の時代背景を考えると、実り豊かな土地は、そこに暮らす人々に恵みをもたらす一方で、その恵みを求める様々な人々の思惑をも惹き寄せてしまうのかもしれない。
その争いは、どのような形で行われたのだろうか。
お互いの血を流す争いまで発展したのか、それとも話し合いの場がもたれ政治的な対話の中でなされたのか。
だが、どのような形であったにせよ、この地で暮らす出雲族にとって、自らの一族の命運を分ける争いであったに違いない。
しかし、幸いにもこの争いは、血で血を洗うような果てのない戦に発展することはなかった。
最終的には、両者の間で和睦を結ぶことで決着を着けることになったのだ。
しかしながら、その交わされた和睦は、出雲族の長の娘であった「伊賀古夜姫」の運命を大きく変えてゆくことになるのだ。

託された運命の縁
その和睦の印として定められたのは、出雲族の女性を相手側の一族の長の妻とするというものだった。
そして、その女性として選ばれたのが「伊賀古夜姫」だったのだ。
古の時代、そうした婚姻関係を通しての和睦は珍しくなかっただろう。
彼女自身が自らが望んだことなのか、それとも一族を守るため自分の意志を隠しての決断だったのか、それぞれの氏族を越えた愛が二人の間に愛があったのか、その真相を知るすべは今は残されてはいない。
もしかすると彼女には既に心に決めた人がいたのかもしれない。
時代を遡ると、いつの時代も、自分の意志とは異なる運命の荒波に翻弄された女性の姿に出会う。

彼女もまたそんな数奇な運命に巻き込まれていったのだ。
どんな事情があったにせよ、遥か遠い出雲の地から亀岡の地に辿り着き、この地で暮らした多くの出雲族の運命が彼女一人に託されたのだ。
そして、そんな交錯する多様な運命を「伊賀古夜姫」は決して拒むことなく、たった一人で受け止めたのである。
彼女の決断は、多くの出雲族の人々の心を灯したに違いない。
またそんな彼女の生き方を讃え、その後に彼女を一族の女神として祀ってゆくことになる人々の想いも、とても自然な流れのように感じられる。
そんな様々な運命をたった一人で背負いながら、「伊賀古夜姫命」は出雲族を離れ、異なる一族の一員として、新たな一歩を踏み出してゆくのだ。
そして、そんな彼女の新たな歩みこそが聖なる地を育む大いなる縁へと繋がってゆくのである。
- text / photo HAS
Reference :
-
「宮前町のしおり(2019年作成)」
- 発行:
- 宮前町自治会
-
「丹波物語」
- 出版:
- 国書刊行会
- 著者:
- 麻井 玖美、角田 直美
-
「出雲大神宮史 : 丹波國一之宮」
- 出版:
- 出雲大神宮社殿創建千三百年大祭記念事業奉賛会
- 著者:
- 上田正昭 監修・編纂委員長
- 編集:
- 出雲大神宮史編纂委員会
-
text / photo :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about
-
 [ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ
[ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ -
 [ 前編 ]丹色の波音
[ 前編 ]丹色の波音 -
 [ 中編 ]たなびく雲の旅路
[ 中編 ]たなびく雲の旅路 -
 [ 後編 ]響き合う縁
[ 後編 ]響き合う縁