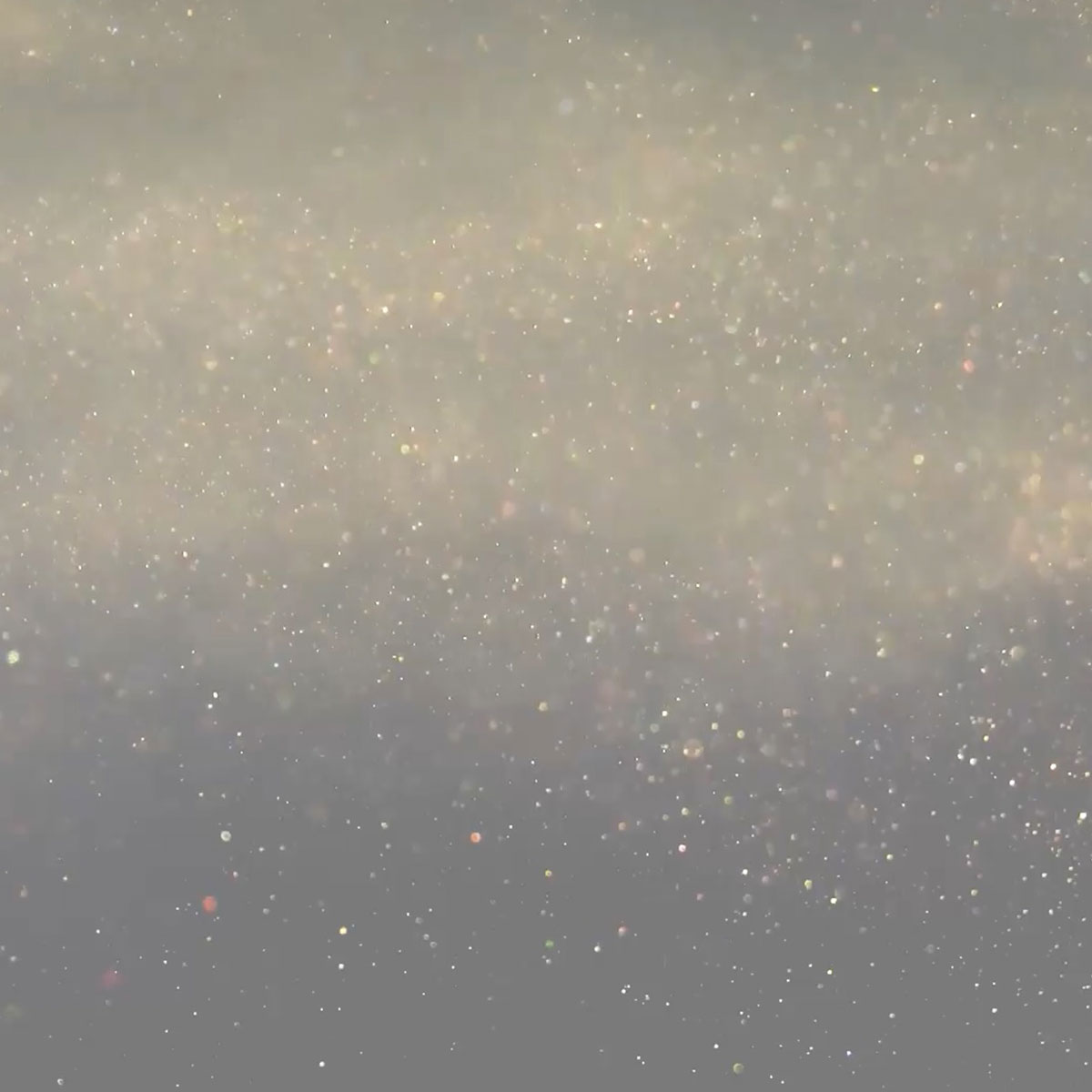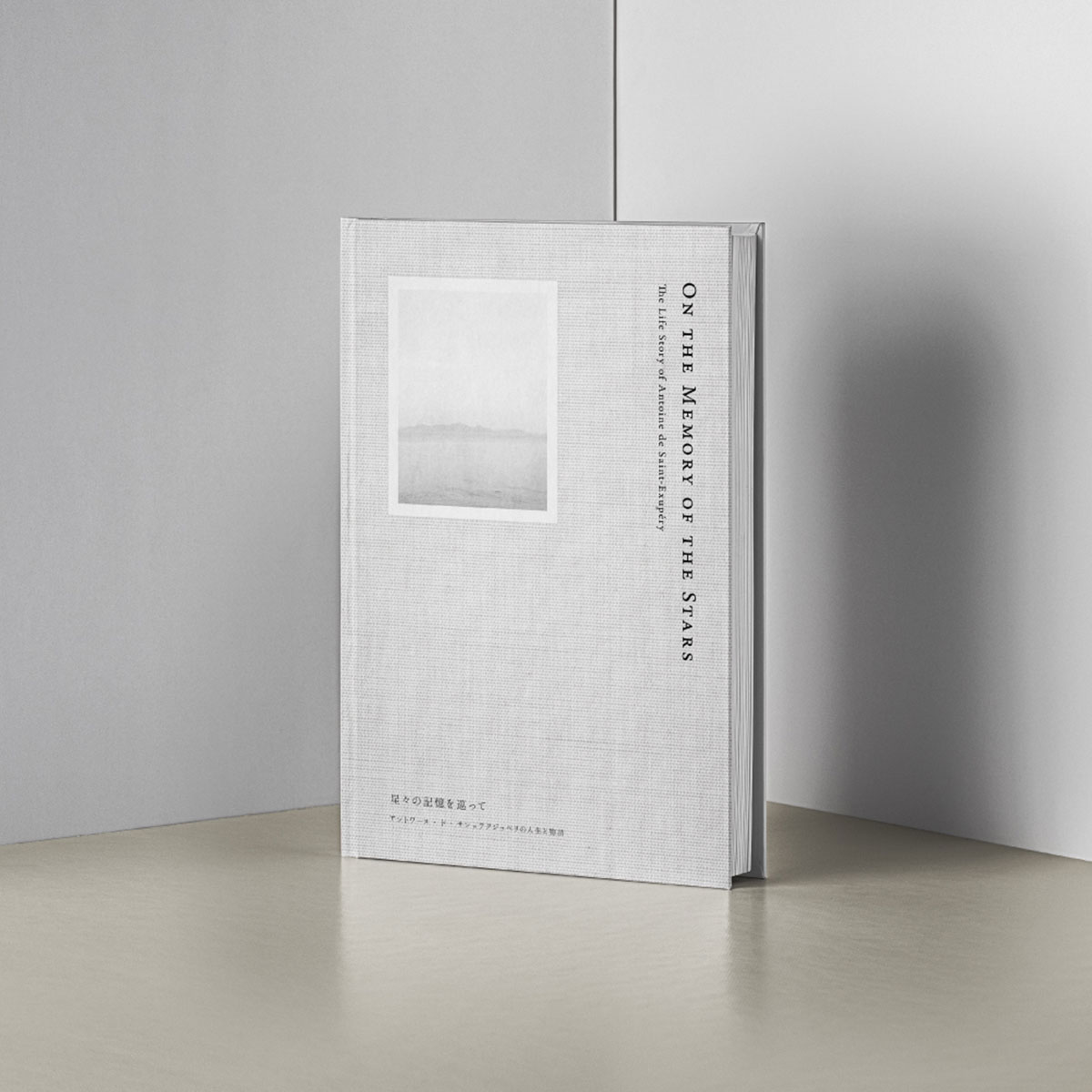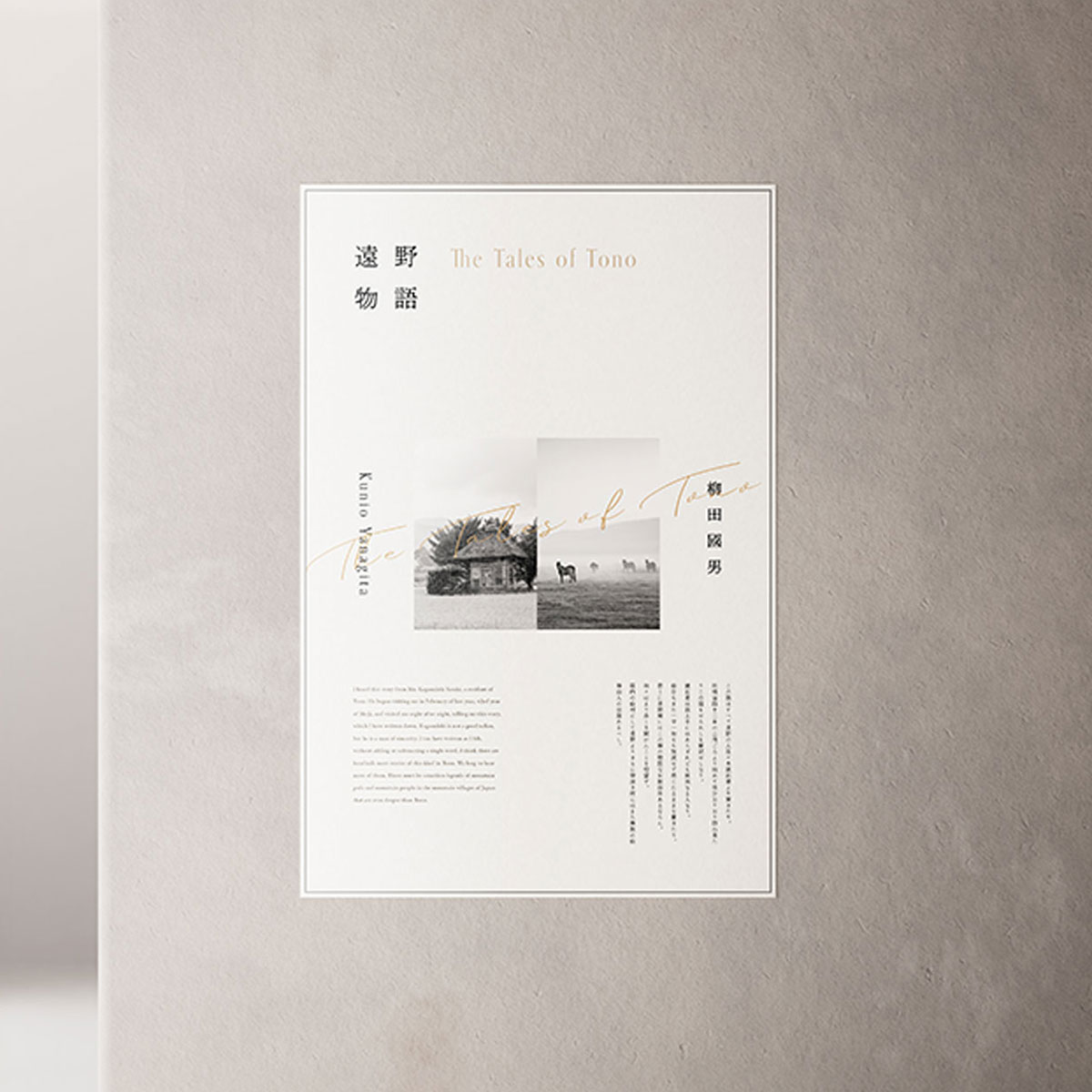- リンクをコピー
- 記事はこちら
色褪せた写真。
その写真に残る記憶を手繰り寄せるように、過ぎ去った日々を思い返す時間。
この音楽は、そんな淡い郷愁を想い描くように紡がれた一曲です。
この曲の歌い手は、かつてドイツで女優として活動していたSibylle Baier シビル・ベイヤー。
彼女は、役者業の傍らで音楽活動を行っていたのですが、当時は作品発表にまでは至りませんでした。
ですが時を経て、ホームレコーディングで録音していた音源を息子が見つけたことをきっかけに、30年後の2006年に唯一のアルバム作品「Colour Green」が発表されました。
この曲には、彼女の音楽が辿った運命のように、まるで時の彼方に忘れ去られたかのような郷愁を帯びた美しい歌声が流れています。
1970年代には女優として活動し、ヴェム・ヴェンダース監督映画「都会のアリス」等に出演する。
その役者の傍ら音楽活動を行うが作品発表にまでは至らなかった。
だが時を経て、ホームレコーディングで録音していた音源を息子が発見する。
その音源をダイナソーJr.のJ.マスシスに手渡したことがきっかけとなり、30年後の2006年に唯一のアルバム作品「Colour Green」が発表された。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
澄み渡る空気と沈黙に包まれた静かな夜のひと時。 この音楽は、そんな静謐な時の中で、まるで水面に一滴の水が落とされるように紡がれたピアノ曲です。
「The Malady of Elegance」と名付けられたアルバムに収録された一曲。 この曲は、アメリカ・ペンシルベニア州出身の音楽家 キース・ケニフによるプロジェクト Goldmundの楽曲として紡がれました。
沈黙に捧げられるように静か紡がれるピアノの響きが静寂の中にある美しさを私たちに教えてくれます。
彼の音楽表現は多岐に渡り、表現するジャンル毎に、Helios/Mint Julep/Keith Kenniffといった多様な名義を使い分け、様々作品を発表し続けている。
Goldmundという名義では、主にピアノを用い、空間を静かに響かせるような美しい音楽を制作している。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
雲もまた自分のやうだ
自分のやうに
すつかり途方にくれてゐるのだ
あまりにあまりにひろすぎる
涯のない蒼空なので
おう老子よ
こんなときだ
にこにことして
ひよつこりとでてきませんか
本名、土田八九十(つちだ はくじゅう)。
1909年、人見東明から「静かな山村の夕暮れの空に飛んでいく鳥」という意味をこめ「山村暮鳥」の筆名をもらう。
築地の聖三一神学校時代に文学に開眼し、卒業後はキリスト教の伝道師として各地で布教活動をしながら詩を書き続け、数多くの作品を生み出した。
代表作は『聖三稜玻璃』(1915年)、『風は草木にささやいた』(1918年)、『雲』(1925年)など。
- 著者 山村暮鳥
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 80
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
- リンクをコピー
- 記事はこちら
優しい日差しに包まれた昼下がりのひと時。 この音楽は、そんな午後の穏やかな陽だまりを描くように紡がれた一曲です。
この歌の主は、アメリカ・オレゴン州の小さな町コキール出身の女性シンガーソングライターのLaura Gibson ローラ・ギブソン。
「If You Come To Greet Me」と名付けられたアルバムに収録されています。
穏やかな陽だまりが心をゆっくりとほどいてゆくように、聴く人の心を穏やかに灯してくれる音楽です。
ニューヨークとオレゴンを拠点に、四大陸でのツアーを行うなど世界各地で音楽活動を行っている。 伝統的な民族音楽と実験的な精神の両方を大切にしながら領域にとらわれない幅広い音楽制作を行っている。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
アメリカ合衆国サンフランシスコ州ロサンゼルスを拠点に活動する、アンビエント作家 marine eyes(マリーン・アイズ)こと、シンシア・バーナードによる一曲。
「what’s on the inside」と名付けられたこの曲は、彼女のアルバム「chamomile カモミール」の中に収められています。
アルバム名の「chamomile カモミール」とは、ハーブティーとしても良く用いられる植物の名前から付けられたもの。
仕事の合間に自らの記憶を手繰り寄せるように日記を書きながら、カモミールティーを飲む時間は、心を自らの中心に戻す大切な時間だと語っています。
彼女にとって「chamomile カモミール」とは落ち着きの象徴であり、自らの心の中に平穏を取り戻す力となるもの。
このアルバムには、彼女がカモミールティーを飲みながら、これまで綴った日記のページをめくるように、彼女の目にした様々な美しい風景が詰まっています。
楽曲のタイトル「what’s on the inside」とは、「心の内側では何が起きているの?」という意味。
朧げで美しい光に包まれるようなこの曲は、聴く人を遥か遠い記憶の彼方に導いてくれるような気がします。
柔らかな光に包まれる静かな朝、静まり返った真夜中に、ふと穏やかな記憶の灯を届けてくれる美しい一曲です。
幽玄で美しいヴォーカルとフィールド・レコーディングやギター、シンセサイザーを重ね合わせながら、温かく穏やかなサウンドスケープを描き出している。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
短い日照時間によって、長い暗闇に包まれる北欧の冬。
この音楽は、そんな冬の闇に暖かな光を灯すように紡がれたピアノ曲です。
彼の初となるピアノソロ・アルバム「Pinô」に収録された、アルバム名と同じ名前の一曲。
この曲は、ノルウェー出身の音楽家 Otto A Totland オット・A・トットランドによって生み出されました。
まるで穏やかな春の日を想わせる、どこか優しく、柔らかな温もりに包まれたこの曲は、北欧の長い冬の先にある微かな春の光を私たちに感じさせてくれます。
トラックメイキングから音楽制作を始め、その後ピアノでの作曲を行うようになる。
憂いを帯びた美しいサウンドスケープを描く「Deaf Center」のメンバーとしての音楽活動を経て、2014年に初のソロピアノ作品「Pino」を発表した。
ひとつひとつのピアノの音色を丁寧に紡ぐ、優しい音楽を紡いでいる。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
吹き抜ける風、やわらかな木漏れ日、穏やかな川のせせらぎ。 美しい自然が訪れる人をそっと包み込むような場所。 この音楽には、まるでそんな安息の地へと誘うような優しい歌声が流れています。
「A Plea En Vendredi」というアルバムの中に収められた一曲。 この曲は、オーストラリア出身の学者であり、シンガーソングライターのタマズ・ウェルズによって紡がれました。
聴く人の心を優しく包み込むような彼の歌は、安らぎの地の穏やかな木漏れ日のように、あたたかな時間を私たちに届けてくれます。
彼は、2006年から2012年の6年間をミャンマーで過ごし、現地のNGOでHIV/エイズ教育のヘルスワーカーやフィールドワーカーの仕事をしていた。
その後メルボルンに戻り、メルボルン大学でビルマ政治学の博士号を取得し、現在は学者として暮らしている。
そんな彼の奏でる歌声は、澄み切った優しさに包まれ、「天使の歌声」とも称される。
異色の経歴を持つシンガーソングライターである。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
青々と澄み切った湖面を包むように流れる霧。
この音楽は、そんな霧に包まれた静かな湖面に朧げに射す朝の光のような美しさを湛えた音響作品です。
「Cendre」フランス語で「灰」という意味を持つ名前のアルバムに収録された一曲。
この曲は、オーストリア出身の音楽家 クリスチャン・フェネスと坂本龍一の二人のコラボレーションによって生まれました。
静かに、ささやくように紡がれる美しい響きが澄み切った静謐な時間を私たちの暮らしの中に届けてくれます。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
ある穏やかな午後の日。 ふと見上げた木々の隙間からこぼれ落ちる木漏れ日。 この音楽は、そんな穏やかな木漏れ日をすくい上げるように紡がれたピアノ曲です。
この曲を紡いだのは、デンマーク出身のピアニスト・作曲家である、ヤコブ・デイビッド(Jacob David)。 あたたかな木漏れ日が安らぎのひと時を描くように、穏やかな時間を私たちの暮らしの中に届けてくれます。
デンマークの首都であり、北欧最大の都市であるコペンハーゲンを拠点に活動を行う。
幼少期よりピアノに親しみ、ブルースからクラシックまで幅広い即興演奏を行いながら自身のスタイルを確立。
柔らかなピアノのタッチから紡がれる穏やかな音色が印象的な音楽家である。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
水の辺りに零れる
響ない真昼の樹魂。
物のおもひの降り注ぐ
はてしなさ。
充ちて消えゆく
もだしの応へ。
水のほとりに生もなく死もなく、
声ない歌、
書かれぬ詩、
いづれか美しからぬ自らがあらう?
たまたま過ぎる人の姿、獣のかげ、
それは皆遠くへ行くのだ。
色、
香、
光り、
永遠に続く中。
1917(大正6)年、犬吠岬にて溺れた友人の今井白楊を助けようとし海に入るが、そのまま帰らぬ人となってしまう。享年27歳。あまりに早い最期だった。
- 著者 三富朽葉
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 80
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
- リンクをコピー
- 記事はこちら
内省的な深い青色によって描かれる数々の作品には、独自の静謐な世界観が流れている。日本のみならず欧州の様々な土地を訪れ、その経験を通して自らの感性を磨いていった遍歴の画家である。
- 著者 東山魁夷
- 出版 ビジョン企画出版社
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 69
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
- リンクをコピー