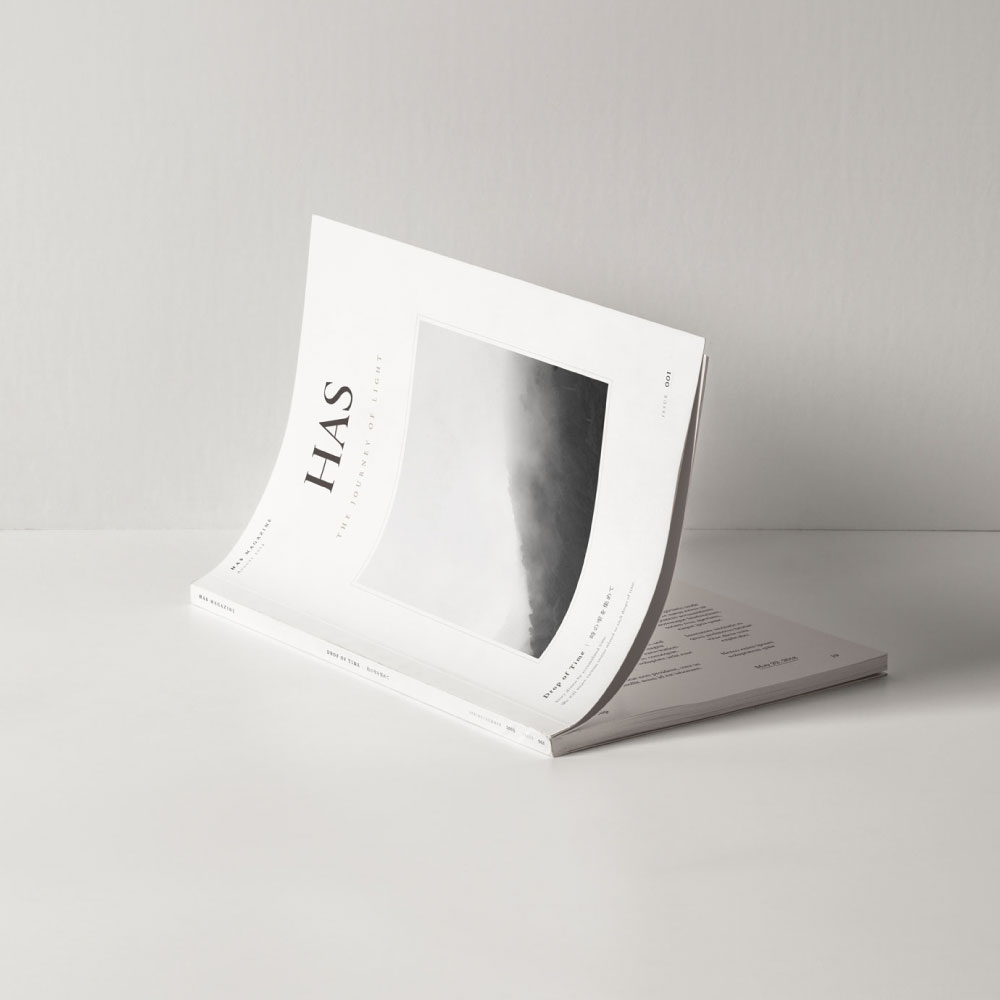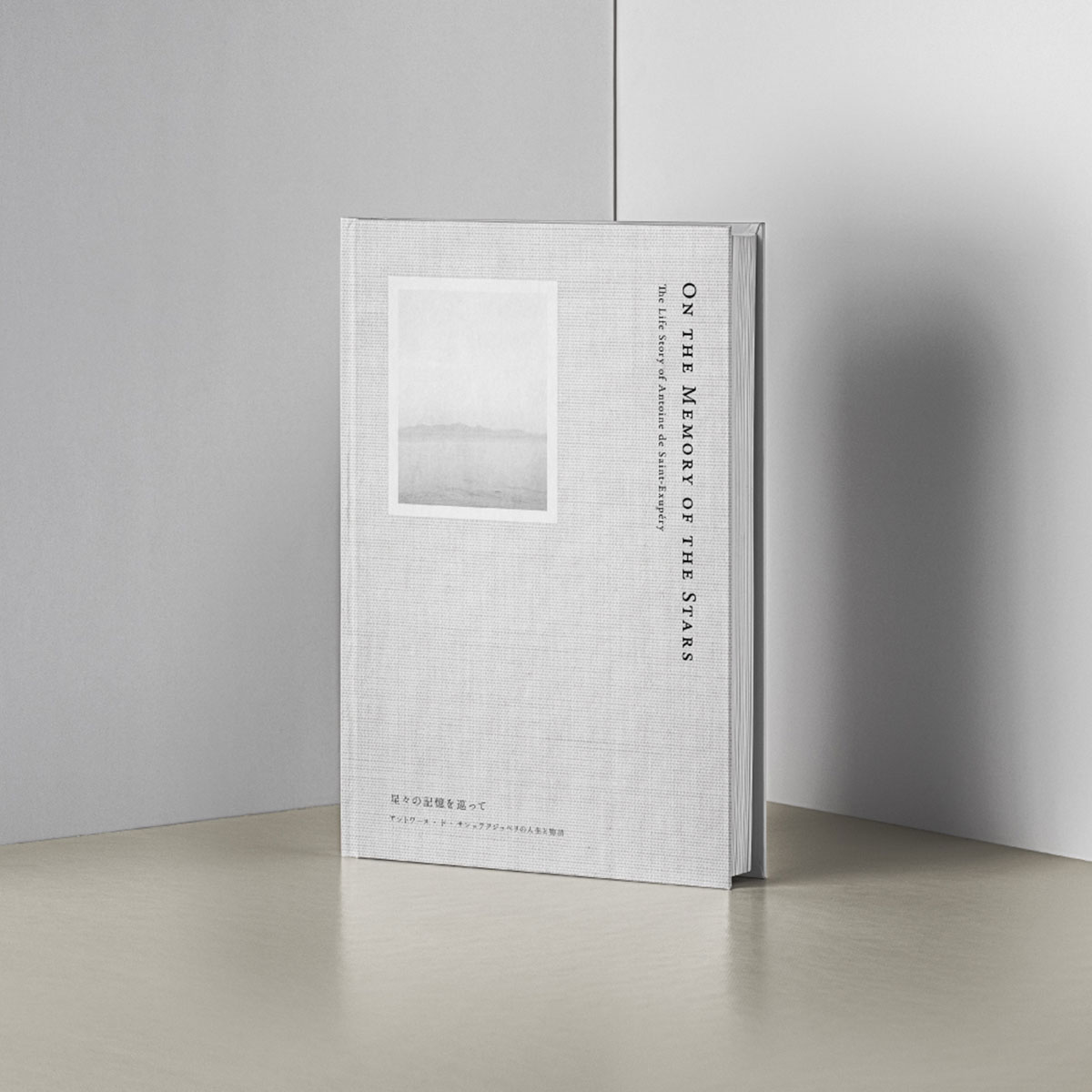暮らしに寄り添う美しい詩をご紹介する「暮らしの詩集」。
今回は、「夜の春雷」という詩をご紹介します。
これは、かつて戦争に赴いた一人の日本の若者によって紡がれた詩です。
今世界は、大きな争いの中に巻き込まれつつあるように感じます。
2022年の春先にウクライナの地で突如として始まった軍事侵攻。
そして、その僅か一年半後の先月初旬には、中東でまた新たな争いが勃発しました。
遥か遠い海の彼方に生きる私たちにとって、それぞれの土地の悲惨な現状は、ともすると、どこか現実感を持って向き合うことが難しいかもしれません。
あるいはまた、そうした厳しい現実に対して、何も出来ない無力さを感じられる方もいっしゃるかもしれません。
しかし、何か具体的なものを届けることは出来ずとも、その現実をしっかりと見つめること、そしてその根本にある問題に想いを巡らせることだけでも大きな意味を持つのではないでしょうか。
この詩は、戦争を通して失われていった、幾つもの物語を想うきっかけとなる詩です。
この詩を紡いだのは、以前ご紹介した「水汲み」という詩を残した、田辺利宏という一人の詩人。
彼が生きた時代は、今から遡ること約80年ほど前のこと。
その時代は、まさに日本が第二次世界大戦へと突き進もうとする時代でもありました。
田辺利宏
1915年5月19日生まれ。岡山県出身。
30年4月、上京して神田の帝国書院に勤めながら、法政大学商業学校に通う。
34年4月、商業学校を卒業し、日本大学予科文科に入学。
36年3月、同大学文学部文学科英文科進学、39年卒業。
39年9月、広島県福山市の増川高等女学校に勤め、英語と国語を教える。
39年12月、松江に入営。後中国各地を転戦。
41年8月24日、中国江蘇省北部にて戦死。享年26歳。
- text / photo HAS / Hiroaki Watanabe
Reference :
-
「きけ わだつみのこえ - 日本戦没学生の手記」
- 編集:
- 日本戦没学生記念会
- 出版:
- 岩波文庫
-
text / photo :HAS ディレクター / デザイナー。 神戸市出身 京都在住。
立命館大学産業社会学部在学中に、インディペンデントの音楽イベントの企画・運営に携わる。
卒業後は環境音楽の制作を開始。その後、独学でウェブ・グラフィックデザインを学び、2019年にHAS創業。
暮らしを灯す物語をテーマに、デザイン、言葉、写真、音楽を重ね合わせながら制作を行う。HAS : www.has-story.jp