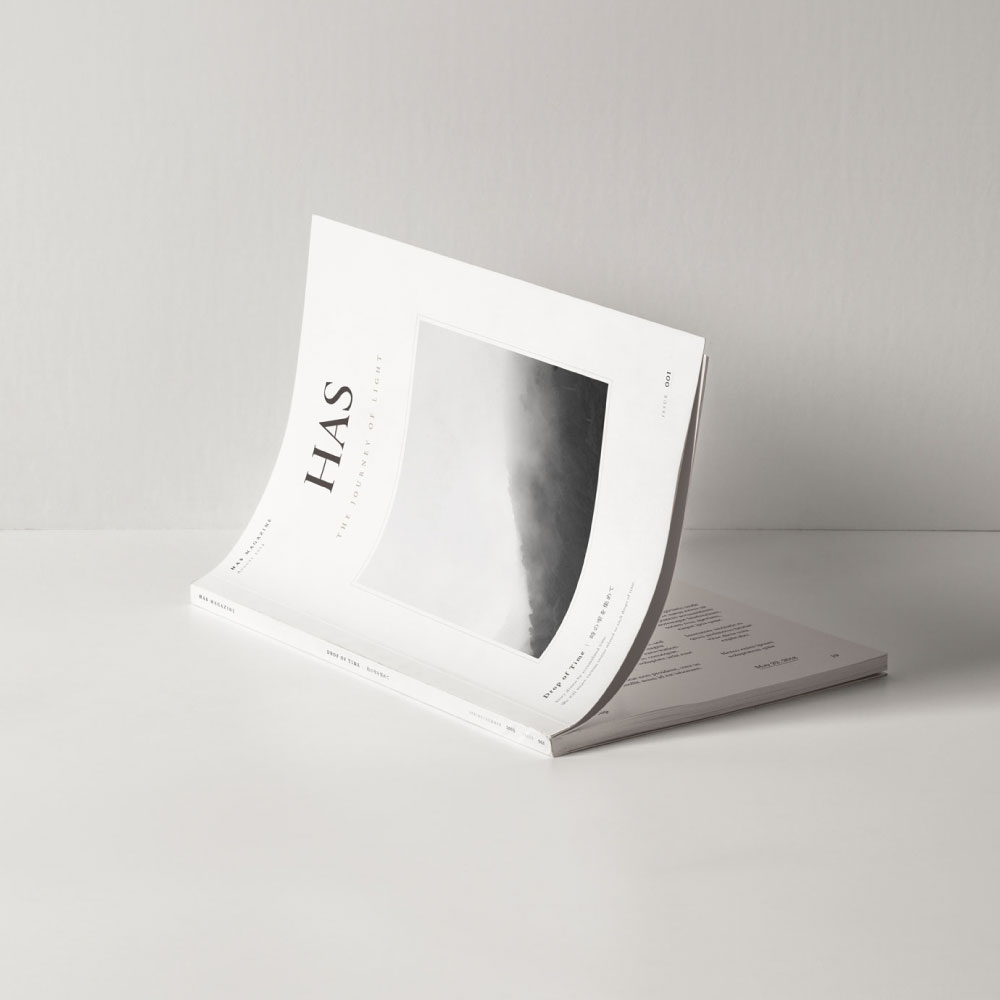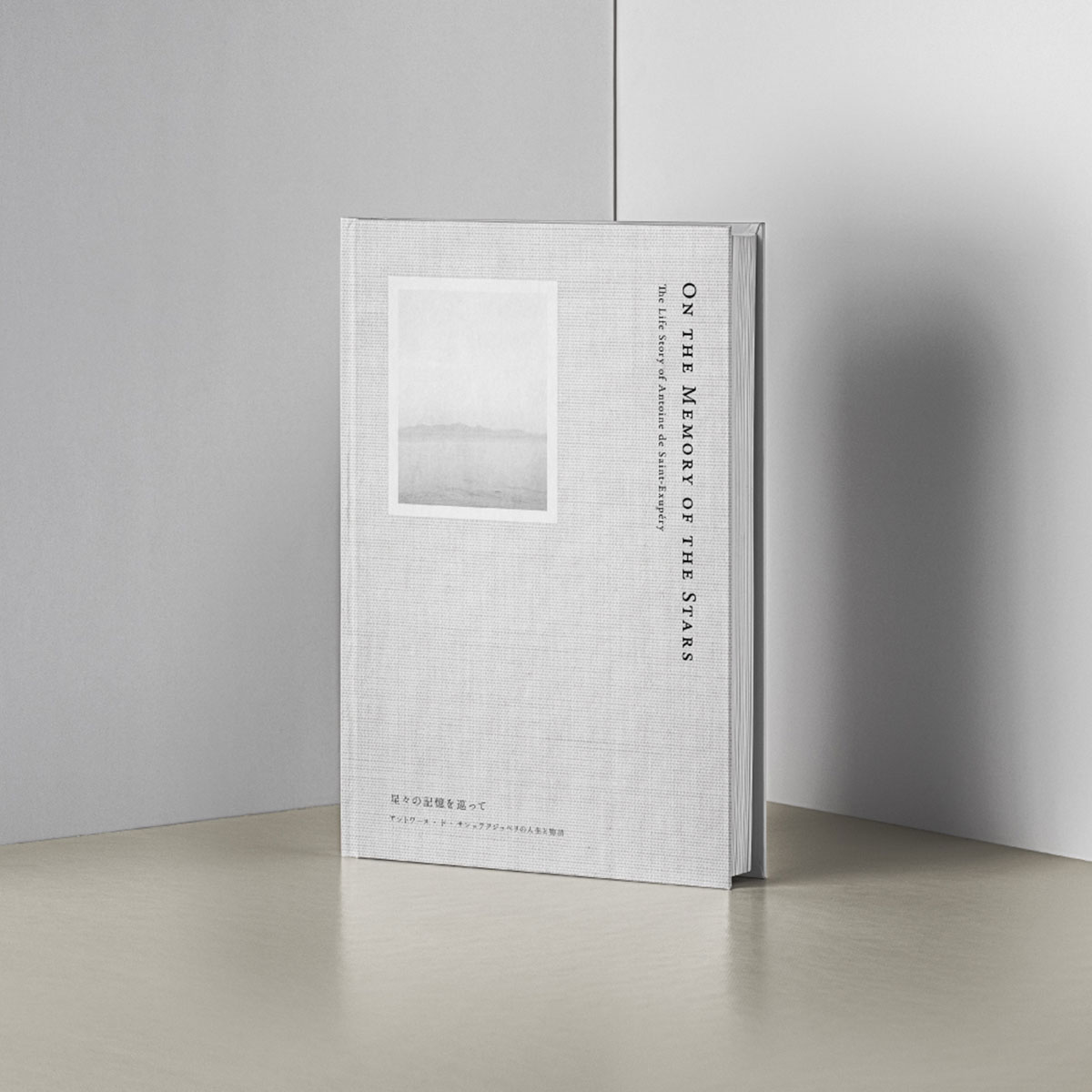水の都・大阪の
知と美の記憶を求めて
知と美の記憶を求めて
of Osaka

of Osaka
かつて大阪は「アドリア海の女王」とも称されたイタリアが誇る水の都「ヴェネツィア」を見立て「東洋のベニス」と謳われた。
都市の中を網の目のように張り巡らされた水路。
その水路を人々が行き交いながら描かれる美しい都市の風景。
それはまさに日本が世界に誇る「水の都」であった。
そんな水の都・大阪の多様な物語を辿りながら、大阪の町に息づく「知」と「美」の記憶を紐解いてゆく「水の都・大阪の知と美の記憶を求めて」。
最終話となる「第5章」のタイトルは、「映し出された記憶」。
今回の物語では、大阪の人々が育んだ町人文化の中心を担った、もう一人の作家の物語を辿ってゆく。
- text / photo HAS
-
 [ 序章 ]知と美の記憶を求めて
[ 序章 ]知と美の記憶を求めて -
 [ 第1章 ]水の都の記憶を辿る
[ 第1章 ]水の都の記憶を辿る -
 [ 第2章 ]栄枯盛衰の先に
[ 第2章 ]栄枯盛衰の先に -
 [ 第3章 ]人々が紡いだ知の記憶
[ 第3章 ]人々が紡いだ知の記憶 -
 [ 第4章 ]曽根崎の森の中で
[ 第4章 ]曽根崎の森の中で -
 [ 第5章 ]映し出された記憶
[ 第5章 ]映し出された記憶
Memories
Memories

もう一人の作家
歓楽の王国へ
水の都・大阪が紡いだ「知」の記憶。
その「知」が育まれた背景をより深く理解するために、その時代に育まれた文化を辿り始めた。
そして、その文化の代表的な作家の一人、近松門左衛門の歩みを紐解いてゆくと、決して杓子定規ではない、あるひとつの美学に辿り着いた。
そんな彼は、大阪を拠点に様々な町人の暮らしから着想を得ながら、数々の作品を生み出した。
人々が自由に生き、活気に満ちた江戸時代の大阪の町は、商人だけでなく様々な作家もまた惹きつけたのである。
当時の大阪を見た「ケンプェル」という長崎のオランダ商館の軍医の旅行記に、ある文章が残されている。

「人口が多いのに、生活が容易であり、毎日のように演劇が行われ、他郷の金持ちや旅行者が集まる。人々はここを歓楽の王国と呼んでいるという。」
まさに大阪は、多くの人々を魅了する「歓楽の王国」であったのだ。
そして、そんな都市の風景をまた別の視点から見つめる一人の人物がいた。
彼の名は「井原西鶴」。
近松門左衛門と同様に元禄文化を代表する作家の一人である。
彼は、町人の暮らしを題材にした「浮世草子」と言う小説のジャンルを生み出し、新たな価値観を大阪の町に届けたのだ。
そんな彼が歩んだ物語を辿りながら、大阪の「美」の記憶をさらに深く辿ってゆきたい。

謎に包まれた生涯
1642年頃、井原西鶴は、大阪で生まれたと言われている。
だがその生涯については未だ不明なことが多い。
現在の和歌山と三重の間にあった紀伊国の中津村が出身地であるとも語られる。
また西鶴は作家としてのペンネームであり、本名は平山藤五であったとも言われる。だがしかし、その真偽も謎に包まれているのだ。
- text / photo HAS
Reference :
-
「大阪商人」
- 著者:
- 武光誠
- 出版:
- ちくま新書
-
「水都大阪物語」
- 著者:
- 橋爪紳也
- 出版:
- 藤原書店
-
「商いの精神」
- 著者:
- 西岡義憲
- 編集:
- 大阪府「なにわ塾」
- 出版監修:
- 教育文化研究所
-
「市民大学の誕生」
- 著者:
- 竹田健二
- 出版:
- 大阪大学出版会
-
「懐徳堂の至宝」
- 著者:
- 湯浅邦弘
- 出版:
- 大阪大学出版会
-
「日本永代蔵」
- 著者:
- 麻生礒次 / 富士昭雄
- 出版:
- 明治書院
-
「西鶴に学ぶ 貧者の教訓・富者の知恵」
- 著者:
- 中嶋隆
- 出版:
- 創元社
-
「上方文化講座・曽根崎心中」
- 著者:
- 大阪市立大学文学研究科「上方文化講座」企画委員会
- 出版:
- 和泉書院
-
「石田梅岩 - 峻厳なる町人道徳家の孤影」
- 著者:
- 森田健司
- 出版:
- かもがわ出版
-
「AD・STUDIES vol.5 2003」
- 発行:
- 財団法人 吉田秀雄記念事業財団
-
text / photo :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about
-
 [ 序章 ]知と美の記憶を求めて
[ 序章 ]知と美の記憶を求めて -
 [ 第1章 ]水の都の記憶を辿る
[ 第1章 ]水の都の記憶を辿る -
 [ 第2章 ]栄枯盛衰の先に
[ 第2章 ]栄枯盛衰の先に -
 [ 第3章 ]人々が紡いだ知の記憶
[ 第3章 ]人々が紡いだ知の記憶 -
 [ 第4章 ]曽根崎の森の中で
[ 第4章 ]曽根崎の森の中で -
 [ 第5章 ]映し出された記憶
[ 第5章 ]映し出された記憶