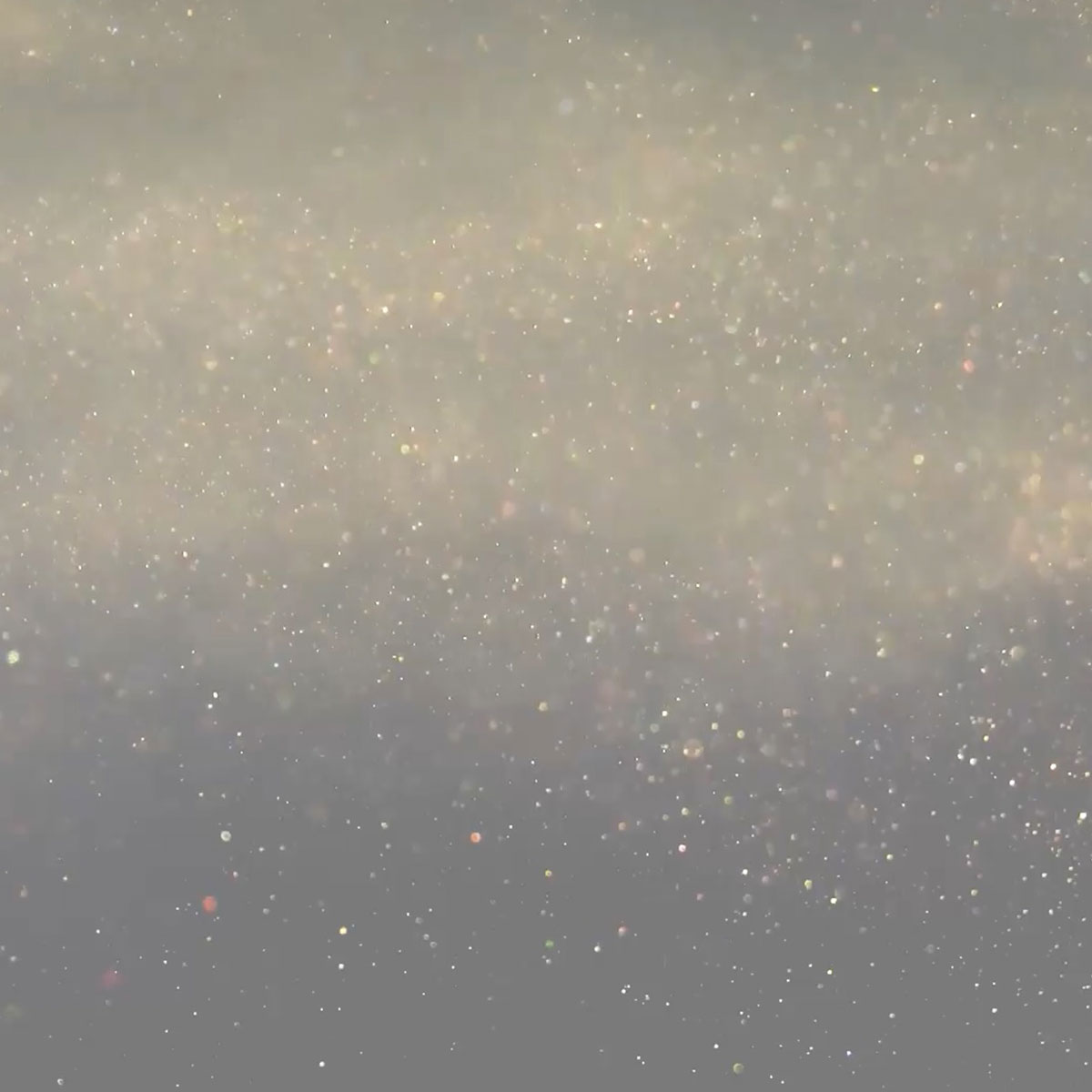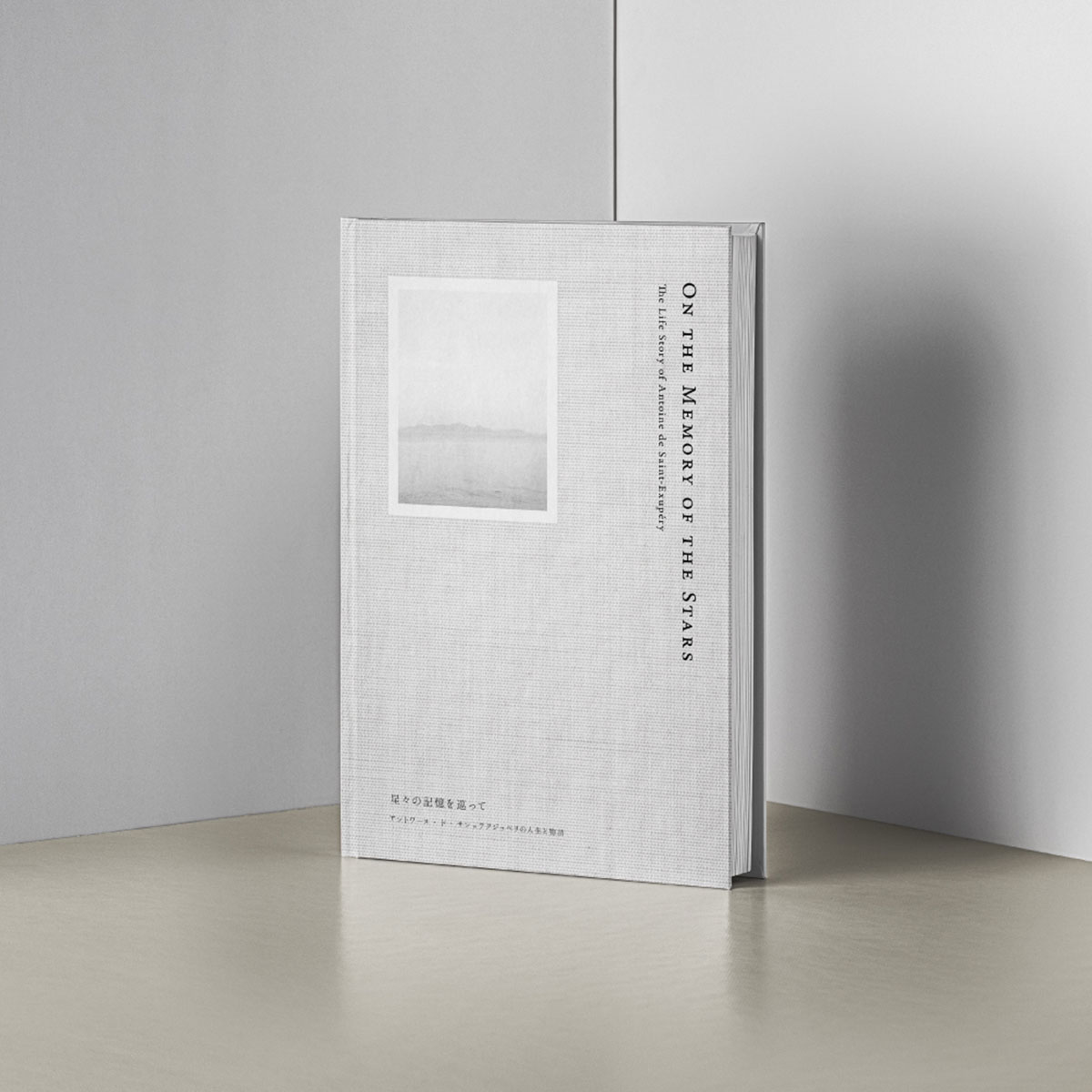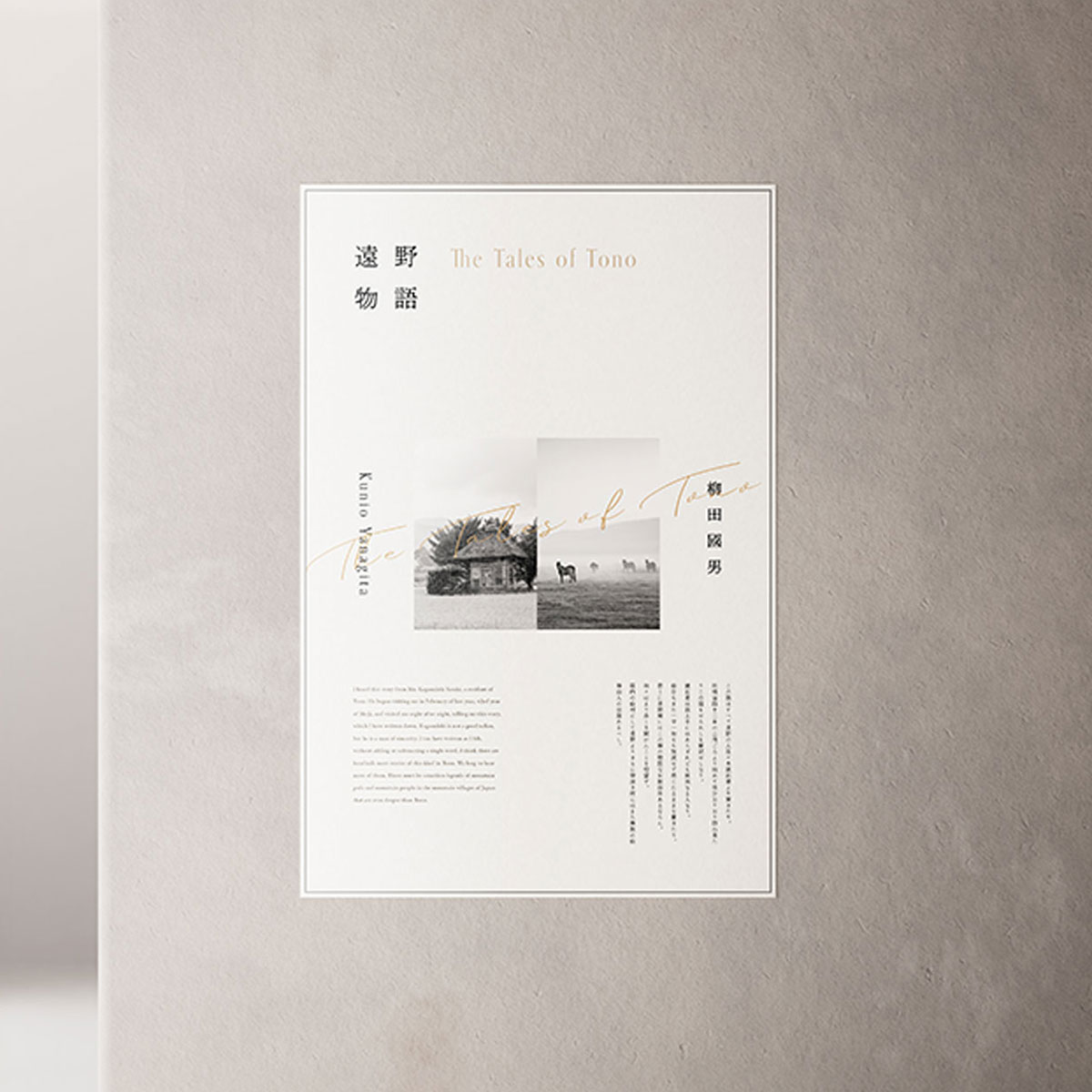- リンクをコピー
- 記事はこちら
そのむかし、わたしの心にさわいだ野獣の嵐が、
初夏の日にひややかによみがへつてきた。
すべての空想のあたらしい核をもとめようとして南洋のながい髪をたれた女鳥のやうに、いたましいほどに狂ひみだれたそのときの一途の心がいまもまた、このおだやかな遊惰の日に法服をきた昔の知り人のやうにやつてきた。
なんといふあてもない寂しさだらう。
白磁の皿にもられたこのみのやうに人を魅する冷たい哀愁がながれでる。
わたしはまことに美の遊行者であつた。
苗床のなかにめぐむ憂ひの芽、望みの芽、
わたしのゆくみちには常にかなしい雨がふる。
早稲田大学第三高等予科を経て、1907年9月、早稲田大学文学学術院英文科に入学。この頃より詩の発表を始める。
1916年にライオン歯磨本舗に就職。以後、生涯をサラリーマンと詩人の二重生活に捧げた。
生涯に書かれた詩作品は2400近くにのぼる。作品の発表を盛んに行っていたものの、生前に詩集が発刊されることはなかった。
- 著者 大手拓次
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/single/single-music.php on line 202
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/single/single-music.php on line 203
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/single/single-music.php on line 203
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/single/single-music.php on line 203
- リンクをコピー
- 記事はこちら
現在の大阪郊外、淀川に近い村で生まれ、20歳前に江戸へ出ると、巴人(はじん)という俳人に師事して俳句を学び始める。
28歳の頃、俳号として「蕪村」を名乗り始め、松尾芭蕉への憧れから10年に近い放浪生活を重ね、42歳のときに京都へ定住した。
絵と俳句の両面で独自の世界観を描き出し、近代の俳人や詩人たちにも大きな影響を与えた。
- 編集 萩原朔太郎
- 著作 与謝蕪村
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 69
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
- リンクをコピー
- 記事はこちら
吹き抜ける風、やわらかな木漏れ日、穏やかな川のせせらぎ。 美しい自然が訪れる人をそっと包み込むような場所。 この音楽には、まるでそんな安息の地へと誘うような優しい歌声が流れています。
「A Plea En Vendredi」というアルバムの中に収められた一曲。 この曲は、オーストラリア出身の学者であり、シンガーソングライターのタマズ・ウェルズによって紡がれました。
聴く人の心を優しく包み込むような彼の歌は、安らぎの地の穏やかな木漏れ日のように、あたたかな時間を私たちに届けてくれます。
彼は、2006年から2012年の6年間をミャンマーで過ごし、現地のNGOでHIV/エイズ教育のヘルスワーカーやフィールドワーカーの仕事をしていた。
その後メルボルンに戻り、メルボルン大学でビルマ政治学の博士号を取得し、現在は学者として暮らしている。
そんな彼の奏でる歌声は、澄み切った優しさに包まれ、「天使の歌声」とも称される。
異色の経歴を持つシンガーソングライターである。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
わが宿の竹の林に、夕あかりかがよふ見れば、
その竹の湿る根ごとに、何か散り、深く光れり。
その節のひとつひとつに、何かまた留り光れり。
その笹のさみどりの葉に、何かまた揺れて光れり。
金色のその光るもの、こまごまと眼に染しみるもの、
雨ふりてあかれるのちは、とりわけて揺れてうつくし。
寂しくて見てゐるきはは、いよいよに消えてうつくし。
揺るるともただ見て居らむ、消ゆるともまた見て居らむ、
堪へ堪へて日の暮るるまで、なほなほに寂しがりつつ。
わがやどの竹の林の夕あかり、裏山松の松風の音のこなたに。
本名は、北原 隆吉(きたはら りゅうきち)、
1904年に早稲田大学に入学と共に上京。明治39(1906)年与謝野寛に誘われ新詩社に参加、『明星』で活躍する。
治42(1909)に第一詩集『邪宗門』を発表。2年後に詩集「思ひ出」を発表すると名実ともに詩壇の第一人者となる。
生涯にわたり多数の優れた詩歌を残し、近代日本を代表する詩人とされている。
- 著者 北原白秋
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 80
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
- リンクをコピー
- 記事はこちら
東京美術学校(東京藝術大学)卒業後、彫刻修業のためアメリカとヨーロッパへ渡る。
パリでロダンに出会い大きな影響を受け、日本を代表する彫刻家であり画家となったが生前に残した『道程』『智恵子抄』などの詩集が広く知られ、日本文学の近現代を代表する詩人として位置づけられている。
- 著者 高村光太郎
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 69
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
- リンクをコピー
- 記事はこちら
青々と澄み切った湖面を包むように流れる霧。
この音楽は、そんな霧に包まれた静かな湖面に朧げに射す朝の光のような美しさを湛えた音響作品です。
「Cendre」フランス語で「灰」という意味を持つ名前のアルバムに収録された一曲。
この曲は、オーストリア出身の音楽家 クリスチャン・フェネスと坂本龍一の二人のコラボレーションによって生まれました。
静かに、ささやくように紡がれる美しい響きが澄み切った静謐な時間を私たちの暮らしの中に届けてくれます。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
アメリカ・ルイジアナ州出身、現在はロサンゼルスを拠点に活動する作曲家・ヴォーカリスト・プロデューサーのジュリアナ・バーウィック(Julianna Barwick)による一曲。
この曲と同じタイトルが付けられたアルバムの題名は『Healing Is A Miracle』。
このアルバムのテーマは「自然治癒能力」。
人間の体が自らを癒す「自然治癒能力」の奇跡のような働きにインスパイアされ、生み出された一曲です。
そんな彼女の歌声が紡ぎ出す幻想的な時間は、耳を傾ける人々の心を穏やかに癒してくれます。
それはまさに彼女が想い描く奇跡のような癒しの力なのかもしれません。
子供時代のルイジアナでの聖歌隊での活動を背景に、自身のヴォーカルをモチーフにサンプラーを用いて幾重にも歌声を重ねながら作曲する、独自のスタイルを持つ音楽家である。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
いけない、いけない
静かにしてゐる此の水に手を触れてはいけない
まして石を投げ込んではいけない
一滴の水の微顫も
無益な千万の波動をつひやすのだ
水の静けさを貴んで
静寂の価を量らなければいけない
あなたは其のさきを私に話してはいけない
あなたの今言はうとしてゐる事は世の中の最大危険の一つだ
口から外へ出さなければいい
出せば則すなはち雷火である
あなたは女だ
男のやうだと言はれても矢張女だ
あの蒼黒い空に汗ばんでゐる円い月だ
世界を夢に導き、刹那を永遠に置きかへようとする月だ
それでいい、それでいい
その夢を現にかへし
永遠を刹那にふり戻してはいけない
その上
この澄みきつた水の中へ
そんなあぶないものを投げ込んではいけない
私の心の静寂は血で買つた宝である
あなたには解りやうのない血を犠牲にした宝である
この静寂は私の生命であり
この静寂は私の神である
しかも気むつかしい神である
夏の夜の食慾にさへも
尚ほ烈しい擾乱を惹き起すのである
あなたはその一点に手を触れようとするのか
いけない、いけない
あなたは静寂の価を量らなければいけない
さもなければ
非常な覚悟をしてかからなければいけない
その一個の石の起す波動は
あなたを襲つてあなたをその渦中に捲き込むかもしれない
百千倍の打撃をあなたに与へるかも知れない
あなたは女だ
これに堪へられるだけの力を作らなければならない
それが出来ようか
あなたは其のさきを私に話してはいけない
いけない、いけない
御覧なさい
煤烟と油じみの停車場も
今は此の月と少し暑くるしい靄との中に
何か偉大な美を包んでゐる宝蔵のやうに見えるではないか
あの青と赤とのシグナルの明りは
無言と送目との間に絶大な役目を果たし
はるかに月夜の情調に歌をあはせてゐる
私は今何かに囲まれてゐる
或る雰囲気に
或る不思議な調節を司つかさどる無形な力に
そして最も貴重な平衡を得てゐる
私の魂は永遠をおもひ
私の肉眼は万物に無限の価値を見る
しづかに、しづかに
私は今或る力に絶えず触れながら
言葉を忘れてゐる
いけない、いけない
静かにしてゐる此の水に手を触れてはいけない
まして石を投げ込んではいけない
東京美術学校(東京藝術大学)卒業後、彫刻修業のためアメリカとヨーロッパへ渡る。
パリでロダンに出会い大きな影響を受け、日本を代表する彫刻家であり画家となったが生前に残した『道程』『智恵子抄』などの詩集が広く知られ、日本文学の近現代を代表する詩人として位置づけられている。
- 著者 高村光太郎
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 80
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
- リンクをコピー
- 記事はこちら
澄み切った水面に零れ落ちる光。
この曲は、そんな自然が描く束の間のひと時をすくい上げるように紡がれた楽曲です。
この曲は、カナダ・サスカチュワン州出身の女性アーティストCharlotte Oleena (シャルロット・オリーナ)によるソロ・ユニット、Sea Oleena (シー・オリーナ)によって紡がれました。
彼女が生まれたカナダ・サスカチュワン州は、広大な草原と十万を数える湖と川が流れ、果てしなく広がる青い空に包まれた雄大な自然が息づく土地。
まるで美しい自然のひと時を紡ぐような彼女の音楽は、そんな彼女の心の中に流れる心象風景を描いたものなのかもしれません。
子供時代にピアノ教室に通うも馴染まず、独学で作曲を始める。その後、偶然実家の空き部屋のベッドの下に、古いアコースティックを見つけたことがきっかけとなり、最初のセルフアルバムを完成する。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
この曲は、ウクライナ・キーウ出身の現代音楽・作曲家 Valentin Silvestrov (ヴァレンティン・シルヴェストロフ)によって紡がれました。
かつて彼は、前衛的な音楽作品を発表していたのですが、ある時期を境に、メロディを重んじた伝統的な作曲手法に回帰するようになりました。
「メロディとは音楽の宝石である。」
(ミュージック・レビュー・サイト『Mikiki』より引用)
これは、彼が過去に美しいメロディーへの想いを語った言葉。
前衛的な現代音楽から消えてしまった美しいメロディーを手繰り寄せるように紡がれた数々の作品の中には、過ぎ去りし日々への静かな祈りが流れているような気がします。
彼が音楽に目覚めたのは15歳と比較的遅く、当初は独学だったが、その後、キエフ夜間音楽学校でピアノを学ぶ。
ソ連支配下の60年代には、前衛的作品で西側から称賛を受けるも、ソ連当局からは冷遇され演奏機会に恵まれなかった。
70年代以降は、調性の破壊と言った前衛的な作曲手法から離れ、メロディーを重んじた伝統的な音楽と現代的な感覚を併せ持つ数々の作品を発表する。
同じく東欧にルーツを持つ、現代音楽を代表する二人の作曲家、アルフレッド・シュニトケとアルヴォ・ペルトをして「現代最高の作曲家のひとり」と称される音楽家である。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
夕影しづかに番の白鷺下り、
槇の葉枯れたる樹下の隠沼にて、
あこがれ歌ふよ。
『その昔、よろこび、そは朝明、光の揺籃に星と眠り、
悲しみ、汝こそとこしへ此処ここに朽ちて、
我が喰み啣める泥土と融とけ沈みぬ。』
愛の羽寄添ひ、青瞳うるむ見れば、
築地の草床、涙を我も垂れつ。
仰げば、夕空さびしき星めざめて、
しぬびの光よ、彩なき夢ゆめの如く、
ほそ糸ほのかに水底に鎖ひける。
哀歓かたみの輪廻は猶も堪へめ、
泥土に似る身ぞ。
ああさは我が隠沼、
かなしみ喰み去る鳥さへえこそ来めや。
啄木は雅号で、本名は石川 一(いしかわ はじめ)。
旧制盛岡中学校中退後、明治35(1902)年与謝野鉄幹の知遇を得て、『明星』に寄稿する浪漫主義詩人として頭角を現す。19歳の時に、処女作となる詩集『あこがれ』を刊行。
同時期に盛岡に帰郷し結婚するも、生活難のため母校の代用教員となる。
明治41(1908)年に上京、創作に没頭し小説を発表するが認められず、困窮の生活を送り、翌年に東京朝日新聞に就職。
明治43(1910)年に『一握の砂』を刊行、歌人としての地位を確立する。
また、同年に起きた幸徳事件(大逆事件)をきっかけに社会主義への関心を深め、文学評論も執筆したが、26歳の時に結核を患い帰らぬ人となる。
- 著者 石川啄木
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 80
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
- リンクをコピー