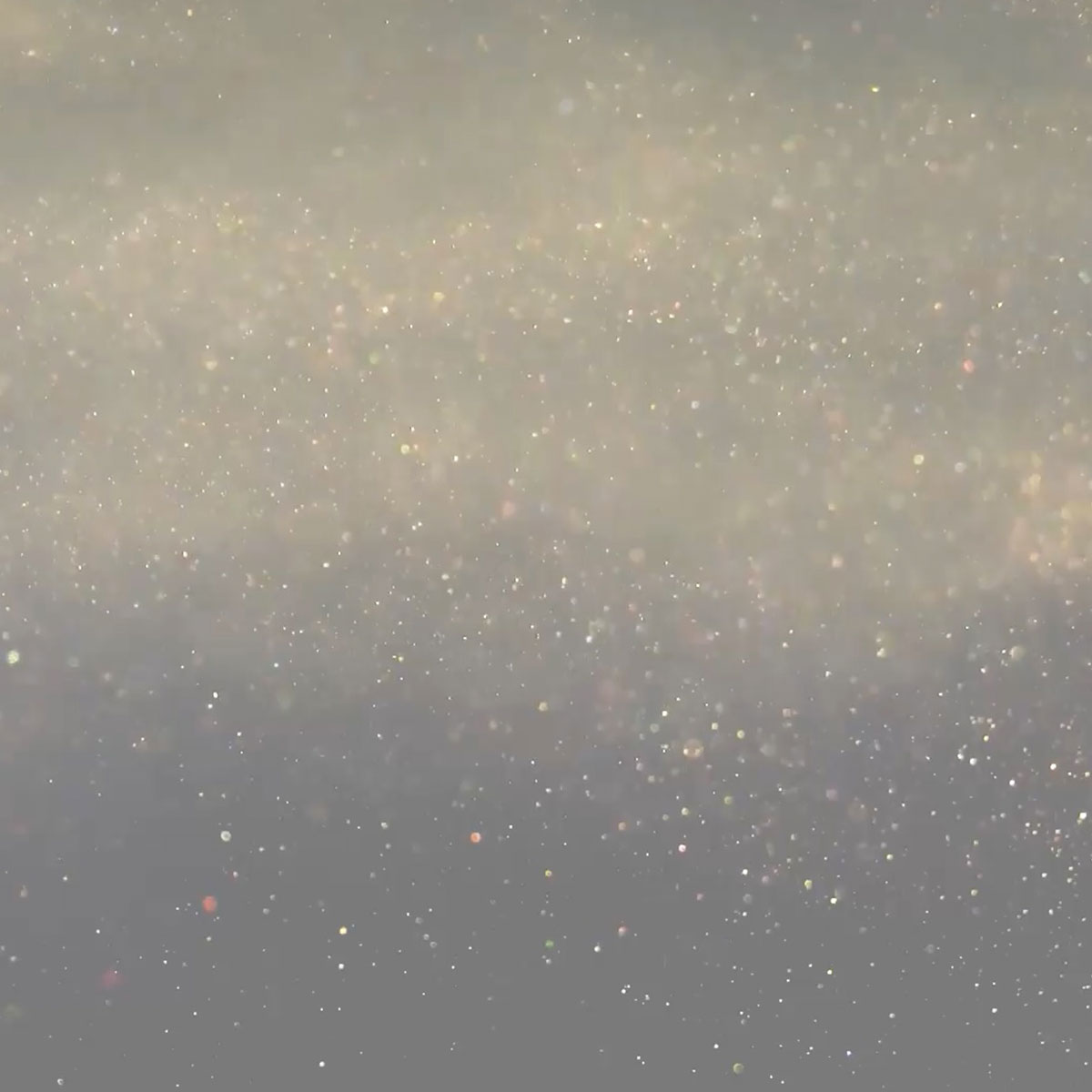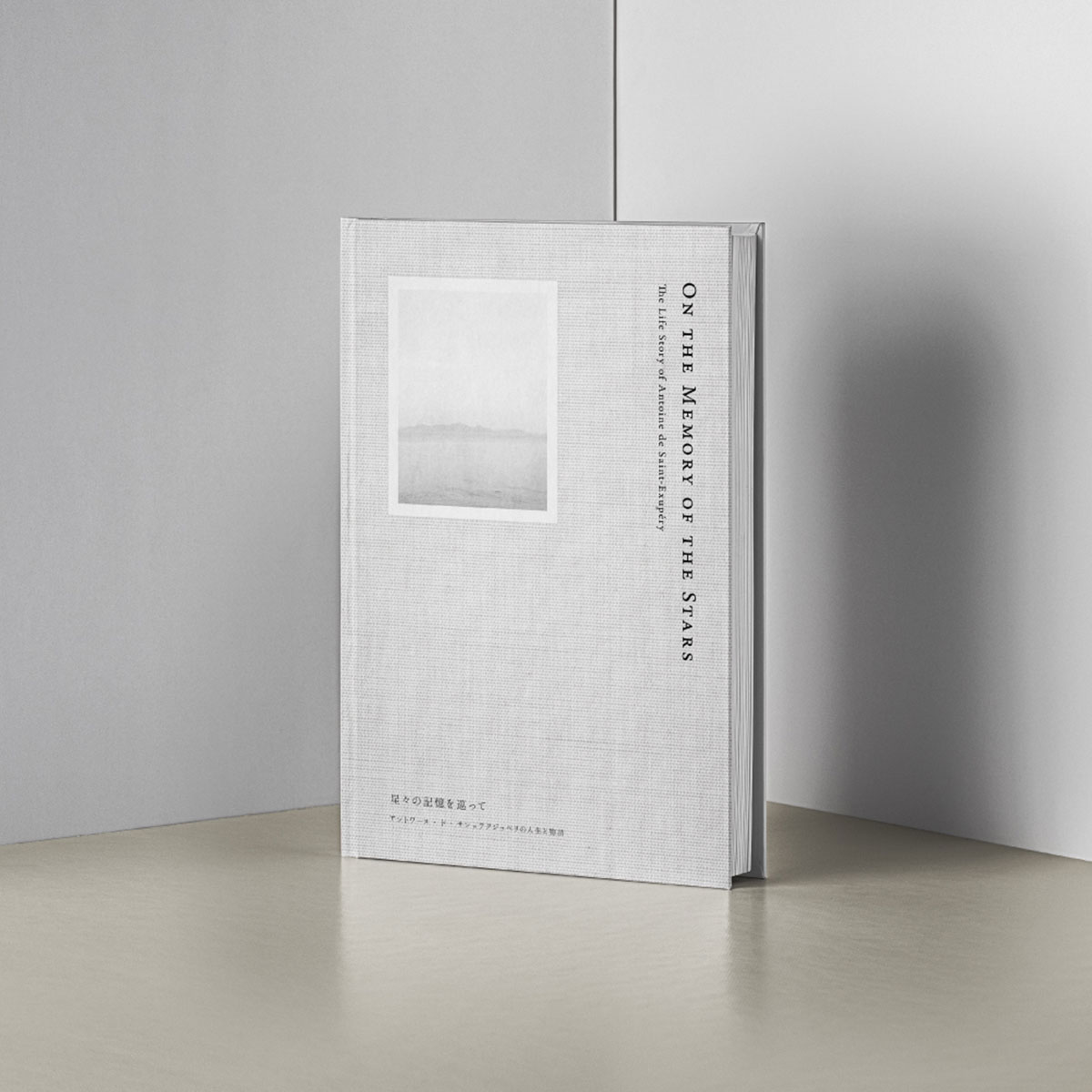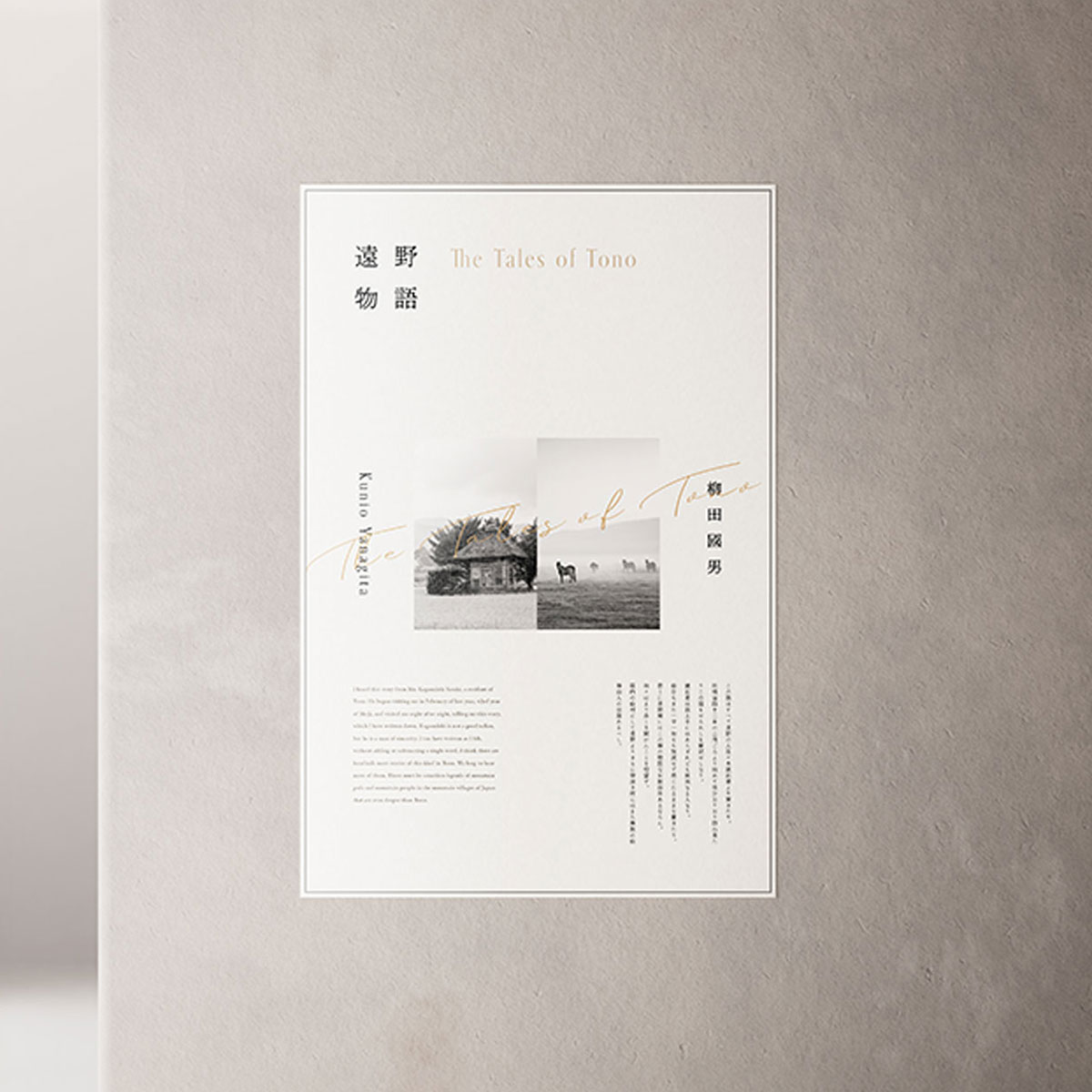- リンクをコピー
- 記事はこちら
朝早くから雨が降つてゐた
そして 暗い日暮れに風が吹いて流れ
雨にとけこむ日暮れを泥ぶかい沼の底の魚のやうに
私と私の妻がゐる 私は二階の書斎に 妻は台所にゐる
これは人のゐない街だ
一人の人もゐない、犬も通らない丁度ま夜中の街をそのままもつて来たやうな気味のわるい街です
街路樹も緑色ではなく
敷石も古るぼけて霧のやうなものにさへぎられてゐる
どことなく顔のやうな街です
風も雨も陽も
ひよつとすると空もない平らな腐れた花の匂ひのする街です
何時頃から人が居なくなつたのか
何故居なくなつたのか
少しもわからない街です
それは
「こんにちは」とも言はずに私の前を通つてゆく
私の旅びとである
そして
私の退屈を淋しがらせるのです
裕福な実家に生まれ、画家を目指して上京、モダニズム絵画「化粧」を発表し、日本のダダイスムの先駆をなす、大正デモクラシーの動向を受けて誕生した前衛美術グループ「MAVO:マヴォ」の初期メンバーとして注目を浴びた。
しかし、2年あまりで美術界を去り、詩作に専念、詩人に転身する。
生涯にわたってほぼ定職を持たず実家からの仕送りで生活し、詩に没頭するという無頼の人生を送った。
- 著者 尾形亀之助
- 出版 青空出版
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/single/single-music.php on line 202
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/single/single-music.php on line 203
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/single/single-music.php on line 203
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/single/single-music.php on line 203
- リンクをコピー
- 記事はこちら
明け方のまだ淡い朝日に照らされた水面の光。
この音楽は、そんな朝の光に溶かされ、淡いオレンジの輝きに染まる水面をすくい上げるように紡がれた音響作品です。
「Shizuku」というアルバムの中に収められた一曲。
この曲は、東京を拠点に活動する音楽ユニットILLUHA イルハによって紡がれました。
アルバムの名前に付けられた「雫」という言葉。
この言葉が表すように、水と光が織りなす美しい雫のような時間を私たちの暮らしに届けてくれます。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
雲もまた自分のやうだ
自分のやうに
すつかり途方にくれてゐるのだ
あまりにあまりにひろすぎる
涯のない蒼空なので
おう老子よ
こんなときだ
にこにことして
ひよつこりとでてきませんか
本名、土田八九十(つちだ はくじゅう)。
1909年、人見東明から「静かな山村の夕暮れの空に飛んでいく鳥」という意味をこめ「山村暮鳥」の筆名をもらう。
築地の聖三一神学校時代に文学に開眼し、卒業後はキリスト教の伝道師として各地で布教活動をしながら詩を書き続け、数多くの作品を生み出した。
代表作は『聖三稜玻璃』(1915年)、『風は草木にささやいた』(1918年)、『雲』(1925年)など。
- 著者 山村暮鳥
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 80
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
- リンクをコピー
- 記事はこちら
わが宿の竹の林に、夕あかりかがよふ見れば、
その竹の湿る根ごとに、何か散り、深く光れり。
その節のひとつひとつに、何かまた留り光れり。
その笹のさみどりの葉に、何かまた揺れて光れり。
金色のその光るもの、こまごまと眼に染しみるもの、
雨ふりてあかれるのちは、とりわけて揺れてうつくし。
寂しくて見てゐるきはは、いよいよに消えてうつくし。
揺るるともただ見て居らむ、消ゆるともまた見て居らむ、
堪へ堪へて日の暮るるまで、なほなほに寂しがりつつ。
わがやどの竹の林の夕あかり、裏山松の松風の音のこなたに。
本名は、北原 隆吉(きたはら りゅうきち)、
1904年に早稲田大学に入学と共に上京。明治39(1906)年与謝野寛に誘われ新詩社に参加、『明星』で活躍する。
治42(1909)に第一詩集『邪宗門』を発表。2年後に詩集「思ひ出」を発表すると名実ともに詩壇の第一人者となる。
生涯にわたり多数の優れた詩歌を残し、近代日本を代表する詩人とされている。
- 著者 北原白秋
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 80
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
- リンクをコピー
- 記事はこちら
中学校2年生の学年試験では、平均84点で102人中3番の成績だったが、3年生の頃から不眠症の徴候があり、4年生進級後も回復しないため退学し、自然に触れながら療養生活の中で短歌に親しんだ。
正岡子規の『歌よみに与ふる書』に深い感銘を受け、1900年に入門。ひたすら子規の写生の風を摂取、子規短歌の最も正当な継承者と言われた。
32歳の時に喉頭結核の診断を下され、各地の病院で治療に努めながら、日本を旅して231首の短歌を発表するも、その4年後の
1915年の2月8日に、福岡県の九州帝国大学医科大学(現九州大学医学部)付属病院で36歳の若さで亡くなった。
- 著者 長塚 節
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 69
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
- リンクをコピー
- 記事はこちら
月の光に照らし出された夜のひと時。 淡い月の光が描く、どこか神秘的な世界。 この音楽は、そんな美しい月の光に寄り添うような一曲です。
「Fairytales」と名付けられたアルバムに収録された一曲。 この曲は、わずか30歳の若さでこの世を去ったノルウェー出身のジャズ・シンガー Radoka Toneff ラドカ・トネフによって紡がれました。
柔らかな月の光が辺りを包み、幻想的な時間が流れ出すように、神秘的で穏やかな美しさを暮らしの中に届けてくれます。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
沖の汐風吹きあれて
白波いたくほゆるとき、
夕月波にしづむとき、
黒暗よもを襲ふとき、
空のあなたにわが舟を
導く星の光あり。
ながき我世の夢さめて
むくろの土に返るとき、
心のなやみ終るとき、
罪のほだしの解くるとき、
墓のあなたに我魂を
導びく神の御聲あり。
嘆き、わづらひ、くるしみの
海にいのちの舟うけて
夢にも泣くか塵の子よ、
浮世の波の仇騷ぎ
雨風いかにあらぶとも
忍べ、とこよの花にほふ
港入江の春告げて、
流るゝ川に言葉あり、
燃ゆる焔に思想あり、
空行く雲に啓示あり、
夜半の嵐に諫誡あり、
人の心に希望あり。
本名は、土井 林吉(つちい りんきち)。
裕福な商家に生まれ、幼少期より学問への強い興味を持っていたが、商人に学問は不要と祖父の強い反対を受け、当初は学問の道を諦め、家業を継ぐために働き始める。だが学問への想いは消えず、仕事の合間を縫い、独り学び続けた。
その熱意にほだされ、最終的に祖父も進学の道を認め、本格的に学問への道に進む。
その後、東京帝国大学英文科に進み、学業の傍らで様々な詩を発表する。
男性的な漢詩調の詩風で、女性的な詩風の島崎藤村と並んで「藤晩時代」と称された。
瀧廉太郎の作曲の「荒城の月」の作詞者としても知られ、校歌も数多く作詞した。
英文学者としは、ホメロス、カーライル、バイロンなどを翻訳。日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章者。
- 著者 土井 晩翠
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 80
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
- リンクをコピー
- 記事はこちら
水の辺りに零れる
響ない真昼の樹魂。
物のおもひの降り注ぐ
はてしなさ。
充ちて消えゆく
もだしの応へ。
水のほとりに生もなく死もなく、
声ない歌、
書かれぬ詩、
いづれか美しからぬ自らがあらう?
たまたま過ぎる人の姿、獣のかげ、
それは皆遠くへ行くのだ。
色、
香、
光り、
永遠に続く中。
1917(大正6)年、犬吠岬にて溺れた友人の今井白楊を助けようとし海に入るが、そのまま帰らぬ人となってしまう。享年27歳。あまりに早い最期だった。
- 著者 三富朽葉
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 80
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/poetry-parts.php on line 81
- リンクをコピー
- 記事はこちら
この曲は、ウクライナ・キーウ出身の現代音楽・作曲家 Valentin Silvestrov (ヴァレンティン・シルヴェストロフ)によって紡がれました。
かつて彼は、前衛的な音楽作品を発表していたのですが、ある時期を境に、メロディを重んじた伝統的な作曲手法に回帰するようになりました。
「メロディとは音楽の宝石である。」
(ミュージック・レビュー・サイト『Mikiki』より引用)
これは、彼が過去に美しいメロディーへの想いを語った言葉。
前衛的な現代音楽から消えてしまった美しいメロディーを手繰り寄せるように紡がれた数々の作品の中には、過ぎ去りし日々への静かな祈りが流れているような気がします。
彼が音楽に目覚めたのは15歳と比較的遅く、当初は独学だったが、その後、キエフ夜間音楽学校でピアノを学ぶ。
ソ連支配下の60年代には、前衛的作品で西側から称賛を受けるも、ソ連当局からは冷遇され演奏機会に恵まれなかった。
70年代以降は、調性の破壊と言った前衛的な作曲手法から離れ、メロディーを重んじた伝統的な音楽と現代的な感覚を併せ持つ数々の作品を発表する。
同じく東欧にルーツを持つ、現代音楽を代表する二人の作曲家、アルフレッド・シュニトケとアルヴォ・ペルトをして「現代最高の作曲家のひとり」と称される音楽家である。
- リンクをコピー
- 記事はこちら
若干18歳で『貧しき人々の群』で文壇に鮮烈にデビューし、天才少女と注目された。
女性の自立を追求した作品「伸子」を発表した後、1928年新しい発展をもとめてソ連、ヨーロッパで生活。
その後ソ連を訪れ日本共産党に入党。宮本顕治と結婚。再三検挙されながらも執筆活動を続けた。戦後は民主主義文学運動の出発を宣言。
日本の左翼文学・民主主義文学、さらには日本の近代女流文学を代表する作家の一人である。
- 著者 宮本百合子
- 出版 青空文庫
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 69
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
Warning: Undefined variable $single_number in /home/studiohas/has-mag.jp/public_html/wp-content/themes/HAS_Magazine_2025_1211/template/retreat/words-parts.php on line 70
- リンクをコピー
- 記事はこちら
ふと昔懐かしい友を想い出す時。 心の片隅に残された、かつての記憶が穏やかに灯されてゆきます。 この音楽は、そんな懐かしい友と巡り会う時間を思いおこしてくれる一曲です。
「The Sea & the Rhythm」という曲名と同じ、アルバムに収録された一曲。 この曲は、アメリカ・サウスカロライナ州出身のシンガーソングライター Iron & Wine アイアン・アンド・ワインによって紡がれました。
歩み続ける日々から少し立ち止まり、過ぎ去りし時を想う時間。 そんな穏やかな郷愁に寄り添う美しい音楽です。
その名前は、自身が映画を撮影している際に、偶然雑貨店で見つけたサプリメント「Beef Iron & Wine」から名付けたという。
どこか懐かしい穏やかな歌声を特徴とする音楽家である。
- リンクをコピー